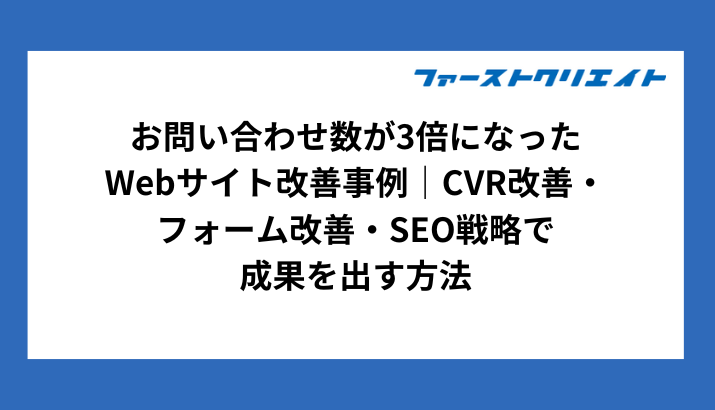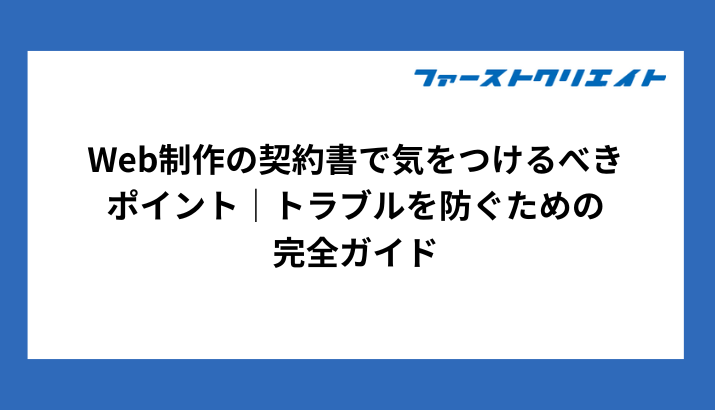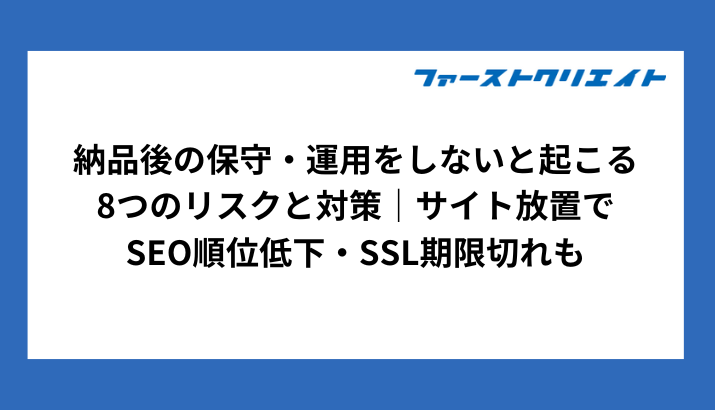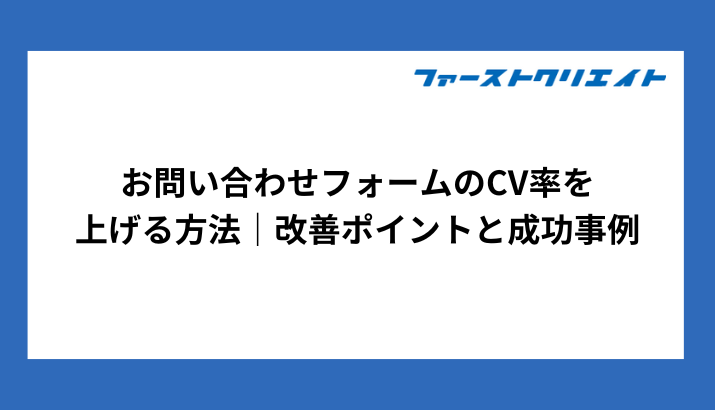お問い合わせフォームのCV率を上げる方法|改善ポイントと成功事例
2025年9月19日
ブログは毎日更新しないとダメ?更新頻度とSEO・集客の関係を解説
2025年10月3日・お問い合わせ数が思うように増えない
・サイト改善をしても成果が出ない
このようなお悩みはありませんか?
お問い合わせ数を伸ばすには、感覚ではなく具体的な改善施策が必要です。フォーム改善やCTAの最適化、SEOとUI/UXの組み合わせにより、実際にお問い合わせ数が3倍に増えた事例もあります。
そこで、この記事では「お問い合わせ数3倍を実現したサイト改善事例」をもとに、CVR改善の方法や継続的な改善プロセスを解説します。内容を読むことで、成果につながる改善ポイントが理解でき、今すぐ実践できるヒントが得られますよ。ぜひ最後までお読みください。
お問い合わせ数が3倍になったサイト改善事例とは?
お問い合わせ数を増やしたいと考える企業は多いです。中でも名古屋のあるWeb制作会社では、サイト改善によってお問い合わせ数を約3倍に伸ばした事例があります。ここではその背景と施策を具体的に紹介します。
最初に問題となっていたのは、サイトを訪れる人がいてもお問い合わせフォームまでたどり着かないことでした。アクセスはあっても問い合わせにつながらない状態は、集客に苦労している中小企業によく見られる課題です。
改善策として取り組んだのは次のような内容です。
- お問い合わせフォームの入力項目を減らす
- ボタンの色や位置を見直し、押しやすい設計に変更する
- スマートフォンからでも使いやすい画面に最適化する
これらの改善は、ユーザーが「すぐに問い合わせたい」と思ったときに行動しやすい環境を整えるための工夫です。入力が簡単になり、ボタンが目に入りやすくなることで離脱率が下がりました。
結果として、問い合わせ件数は以前の約3倍に増加しました。この数値は、ユーザー目線でサイトを改善することがどれほど効果的かを示す明確な証拠といえます。
つまり、お問い合わせ数を増やすためには、自社都合ではなくユーザーの行動しやすさを第一に考えたサイト改善が不可欠です。
サイト改善でお問い合わせ数を増やす重要なポイント
お問い合わせ数を増やすためには、思いつきの変更ではなく、効果的なポイントを押さえた改善が必要です。特にCVR(コンバージョン率)の向上、導線設計の工夫、スマートフォン対応の最適化は成果につながりやすい要素です。ここではそれぞれの観点を詳しく説明します。
CVR(コンバージョン率)改善の基本
CVRとは、サイトに訪れた人のうち実際に行動を起こした割合を指します。例えば100人がサイトを訪れ、そのうち5人が問い合わせをすればCVRは5%です。お問い合わせ数を増やすには、この割合を高めることが不可欠です。
CVRを改善するための基本は以下のとおりです。
- 入力の手間を減らす
- 問い合わせボタンを見つけやすい位置に置く
- 不安を和らげる補足説明を加える
入力の手間が減ると、ユーザーは気軽にフォームに進めます。ボタンが見つけやすければ、次の行動につながりやすくなります。補足説明を入れると、ユーザーは安心して個人情報を入力できます。
つまりCVR改善は、小さな障害を取り除くことから始まります。わずかな工夫でも問い合わせ数を大きく伸ばせるのです。
ユーザー心理に沿った導線設計の工夫
ユーザーがサイト内で迷わず行動できる導線設計は重要です。導線とは、ユーザーがページを移動しながら目的にたどり着く流れを示します。導線がわかりやすいと、お問い合わせに進む確率が高まります。
導線設計の工夫には次のような例があります。
- 商品やサービス紹介ページから直接フォームに移動できるリンクを設置する
- 複数ページに同じCTA(行動喚起ボタン)を置く
- 問い合わせのメリットを目立つ位置で伝える
例えば名古屋のWeb制作会社が行った改善では、サービス紹介ページの下部にフォームへのリンクを加えただけでCVRが上昇しました。リンクがあることで「興味がある今」のタイミングを逃さず行動につながります。
導線設計は、ユーザーが迷わず次の行動を取れる仕組みをつくることが成功の鍵です。
スマホユーザーを意識したレスポンシブ対応
近年はスマートフォンからのアクセスが増えています。レスポンシブ対応とは、パソコンとスマートフォンの両方で見やすく操作しやすいようにデザインを調整することです。スマホ利用者にとって見にくいサイトは、すぐに離脱されてしまいます。
スマホ対応で効果的な工夫は以下のとおりです。
- 文字を読みやすい大きさに設定する
- ボタンを指で押しやすいサイズにする
- 縦スクロールだけで必要情報に到達できるようにする
例えば問い合わせフォームが小さすぎると、入力中に誤操作が増えて離脱につながります。押しやすいボタンと簡単な入力画面にすると、ユーザーは最後まで手続きを完了しやすくなります。
スマホユーザーを意識したレスポンシブ対応は、お問い合わせ数を安定して増やすための必須条件です。
成功事例から学ぶサイト改善の具体的施策
サイト改善の成果を最大化するには、成功事例から具体的な施策を学ぶことが有効です。特にフォームの改善、CTAボタンの見直し、ページ読み込み速度の向上は、多くの企業で成果が報告されています。ここではそれぞれの施策を詳しく見ていきましょう。
フォーム改善で離脱率を下げる方法(入力項目削減・エラーメッセージ改善など)
お問い合わせフォームは、ユーザーが行動する最後の関門です。入力が複雑だと、多くの人が途中で離脱します。名古屋のWeb制作会社が実施した改善例では、フォーム項目を10個から5個に削減したところ、完了率が大幅に上がりました。
フォーム改善の具体策は次のとおりです。
- 必須項目を必要最低限に絞る
- 入力補助(例:郵便番号から住所を自動表示)を導入する
- エラーメッセージをわかりやすく表示する
必須項目が少なければ、ユーザーは負担を感じません。入力補助を導入すると、作業がスムーズになり途中離脱を防げます。さらに、エラーメッセージが明確だと入力ミスをすぐに直せるため、完了までのストレスが減ります。
フォーム改善は、離脱率を下げて問い合わせ完了率を高めるための効果的な施策です。
CTAボタンの配置やデザイン変更による効果
CTA(Call To Action)ボタンとは、行動を促すボタンのことです。例えば「無料で相談する」「資料を請求する」といったボタンが該当します。このボタンの配置やデザインを変えるだけで、お問い合わせ数は大きく変わります。
効果的なCTA改善の方法は次のようになります。
- ファーストビュー(ページを開いた直後の画面)に設置する
- ページを読み進めた後にも繰り返し設置する
- 色や形を目立たせて押しやすくする
名古屋の企業サイトで行われた改善では、CTAをページ上部と下部の両方に配置した結果、クリック率が1.8倍に増加しました。ボタンを見やすく配置することで、ユーザーは行動を先延ばしにせず、すぐに問い合わせに進めます。
CTAの配置やデザイン変更は、行動を後押しし、CVR向上につながるシンプルで強力な方法です。
ページ読み込み速度の改善が与える影響
ページの読み込みが遅いと、ユーザーは待つことにストレスを感じて離脱します。Googleの調査によれば、表示に3秒以上かかると約半数がサイトを離れるとされています。これはお問い合わせ数の大幅な減少につながります。
読み込み速度を改善する具体的な方法は以下のとおりです。
- 画像ファイルを軽量化する
- 不要なプラグインを削除する
- キャッシュ機能を有効活用する
例えば画像を圧縮して容量を半分に減らすだけでも、体感速度は大きく向上します。読み込みが速ければ、ユーザーは離脱せず最後までページを閲覧し、問い合わせへと進む可能性が高まります。
ページ速度改善は、ユーザー体験を向上させ、最終的にお問い合わせ数を増やすための必須施策です。
SEOとUI/UX改善を組み合わせたお問い合わせ増加戦略
お問い合わせ数を大きく伸ばすには、SEOによる集客とUI/UX改善による使いやすさを両立させることが重要です。SEOは検索結果からの流入を増やす施策であり、UI/UX改善はサイト訪問後の行動をスムーズにする工夫です。両方を組み合わせることで、訪問者を効果的に問い合わせへと導けます。
検索流入を増やすコンテンツ最適化
SEOとは、検索エンジンで記事やページを上位に表示させるための施策です。検索流入を増やすためには、読者が求める情報を正確に提供するコンテンツが欠かせません。例えば「名古屋 Web制作会社 お問い合わせ」といった検索を狙い、利用者が知りたい具体的な内容を記事に含めることが効果的です。
コンテンツ最適化のポイントは以下のとおりです。
- サジェストキーワードや関連検索を取り入れる
- 検索意図に合った見出しや本文を構成する
- 具体例や実績を紹介して信頼性を高める
検索流入を増やすことで、見込み客の母数が拡大します。母数が増えれば、UI/UX改善と組み合わせたときに大幅なお問い合わせ増加につながります。
検索流入を増やすコンテンツ最適化は、お問い合わせ数を底上げするための出発点です。
ランディングページの設計とファーストビュー改善
ランディングページとは、ユーザーが最初に訪れるページのことです。最初に目にする画面(ファーストビュー)の印象で、その後の行動が決まるといっても過言ではありません。問い合わせ増加を狙うなら、ランディングページ設計とファーストビューの改善が欠かせません。
効果的な改善方法は次のとおりです。
- キャッチコピーで問い合わせのメリットを端的に伝える
- 視覚的に目立つCTAボタンを設置する
- サービス内容や事例を簡潔に示す
例えば「名古屋で集客に強いWeb制作会社」などのキャッチコピーを配置すると、ユーザーは自分のニーズに合っていると瞬時に理解できます。最初の数秒で魅力を伝えることで、離脱を防ぎ問い合わせにつなげられます。
ランディングページとファーストビューの改善は、ユーザーの心をつかみ行動を引き出す最初の一手です。
内部リンク・導線強化でお問い合わせへの遷移を促す
内部リンクとは、サイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。導線を強化すると、ユーザーが迷わず必要な情報にたどり着きやすくなります。これはSEOにも良い影響を与えると同時に、最終的な問い合わせへの移動をスムーズにします。
具体的な導線強化の工夫は以下です。
- 記事やサービス紹介からフォームページへのリンクを設置する
- 「関連ページ」や「おすすめ記事」を配置して回遊を促す
- ナビゲーションメニューにお問い合わせを常時表示する
例えばサービス詳細を読んだ直後に「今すぐ無料相談」といったリンクがあれば、興味を持ったタイミングで行動につながります。ナビゲーションに常に表示しておけば、ユーザーは迷わず問い合わせに進めます。
内部リンクと導線強化は、ユーザーを自然な流れで問い合わせページに誘導するための実践的な戦略です。
サイト改善に取り組む際の注意点と落とし穴
サイト改善は正しく取り組めば大きな成果をもたらしますが、やり方を誤ると逆効果になることがあります。特に注意したいのは、数字ばかりを追いかけてしまうことや、ユーザーニーズを無視した改修です。さらに、短期的な成果にとらわれすぎて長期的な改善を怠ることも大きな落とし穴になります。
数字だけを追いすぎないリスク
お問い合わせ数やクリック率といった数値は改善の指標として重要です。しかし数字に偏りすぎると、本質を見失うリスクがあります。例えばフォーム送信数を増やすために項目を極端に削減すると、質の低いリードばかりが集まることがあります。
数字にとらわれすぎると、売上や顧客満足度といった本来の目的が達成されにくくなります。名古屋のWeb制作会社でも、初期の改善で数字だけを意識した結果、問い合わせ数は増えたものの受注には結びつかないという課題が発生しました。
数字は大切ですが、ビジネスの最終的な成果につながる改善を意識することが不可欠です。
ユーザーニーズを無視した改修の失敗例
ユーザーの要望や行動を無視した改修は、改善どころか逆効果を生む場合があります。例えばデザインを派手にして目立たせようとした結果、ユーザーが必要な情報を探しにくくなるケースがあります。
よくある失敗例は次のとおりです。
- 問い合わせボタンを増やしすぎて逆に混乱を招く
- 専門用語を多用して読みにくいページになる
- 企業目線の内容ばかりでユーザーの悩みが解決できない
このような改修は、ユーザーの離脱を招きます。Web制作会社が提供する改善支援でも「ユーザー調査を行わずに改修して失敗した」という事例が少なくありません。
ユーザー視点を無視した改修は、成果を遠ざける大きな要因になります。
短期的なテストと長期的な改善のバランス
サイト改善には短期的なテストと長期的な改善の両方が必要です。短期的なテストは仮説を検証しやすく、素早い効果を確認できます。例えばCTAボタンの色を変えるといった小さな変更は数日で結果がわかります。
一方で、長期的な改善はサイト全体の価値を高める施策です。SEO対策やブランドの信頼性向上は時間がかかりますが、持続的な成果を生みます。短期施策だけに依存すると一時的に数字が上がっても、すぐに成果が落ちてしまいます。
バランスを取るためには、短期的な改善で成果を確認しつつ、長期的な施策も同時に進めることが重要です。例えばアクセス解析を活用し、短期的な数値の変化を追いながらも、長期的にSEOを強化する流れをつくると安定的な成長につながります。
短期と長期の両方を意識して改善に取り組むことで、持続的なお問い合わせ増加が実現します。
お問い合わせ数を増やすための継続的な改善プロセス
サイト改善は一度きりでは成果が長続きしません。お問い合わせ数を安定して増やすには、継続的に改善を行うプロセスが必要です。アクセス解析やABテストによる検証、ユーザーフィードバックの活用、さらに低コストで実践できる工夫を組み合わせることで、着実な成果が期待できます。
定期的なアクセス解析とABテストの実施
アクセス解析とは、サイトに訪れるユーザーの行動を数値で把握する仕組みです。例えば「どのページで離脱しているのか」「問い合わせフォームに進む前にどこで迷っているのか」を調べることができます。これにより改善すべき箇所を正確に特定できます。
ABテストは、同じページの異なるパターンを比較してどちらが効果的かを検証する方法です。例えば「青いボタン」と「赤いボタン」を比較して、クリック率が高い方を採用します。名古屋のWeb制作会社でもABテストを行い、色や配置の違いでCVRが20%改善した事例があります。
定期的なアクセス解析とABテストを組み合わせることで、改善の効果を数字で確認しながら着実に前進できます。
ユーザーフィードバックを取り入れた改善サイクル
ユーザーの声は、サイト改善における最も信頼できる情報源です。アンケートやヒアリングを行うと、数字だけでは見えない課題を発見できます。例えば「入力フォームが長くて途中でやめた」という意見があれば、入力項目の削減が有効な改善策となります。
改善サイクルを回す手順は次のようになります。
- ユーザーから意見を集める
- 意見をもとに改善策を考える
- 改善後の結果を再度ユーザーに確認する
この流れを繰り返すことで、ユーザーにとって利用しやすいサイトへと進化していきます。Web制作会社の支援でも、ユーザー調査を取り入れた改善は長期的に成果が出やすいと報告されています。
ユーザーフィードバックを反映することは、数字だけではわからない改善効果を得る最も実践的な方法です。
中小企業でも実践できる低コスト改善アイデア
サイト改善は大きな予算をかけなくても取り組めます。中小企業でも低コストで実践できる方法は多く存在します。例えば無料のアクセス解析ツールを使えば、ユーザーの行動を把握できます。さらにフォームの入力項目を削減するだけでも効果が期待できます。
低コストでできる改善例は以下のとおりです。
- Googleアナリティクスなどの無料ツールを活用する
- 既存ページの見出しをユーザー目線に書き換える
- お問い合わせボタンの色や位置を小規模に変更する
こうした施策は費用をほとんどかけずに始められます。実際に名古屋の中小企業が導入した事例では、わずかな改善でCVRが約1.5倍に上昇しました。
中小企業でも実践できる低コスト改善は、限られた資金の中で成果を最大化するための有効な手段です。
まとめ|お問い合わせ数3倍を実現するための道筋
お問い合わせ数を増やすためには、単発的な工夫ではなく、総合的な改善が必要です。成功事例から見えてきたのは「ユーザーにとって使いやすい環境を整えること」が最も効果的な方法であるという点です。フォームの最適化やCTAの工夫、ページ速度の改善といった具体策は、どれも小さな工夫の積み重ねによって大きな成果を生みます。
さらに、SEOによる検索流入の強化とUI/UX改善を組み合わせることで、訪問者をスムーズにお問い合わせへ導く流れを構築できます。数字の変化を定期的に検証し、ユーザーの声を取り入れるサイクルを続けることが、長期的な成果を維持する鍵です。名古屋のWeb制作会社が示した事例も、こうした地道な取り組みが成果につながったことを裏付けています。
つまり、お問い合わせ数3倍を実現する道筋は、ユーザー視点に立った改善を継続的に積み重ねることにあります。
ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webのことは全然わからないので、一からしっかり説明してくれるWeb制作会社を探している」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。