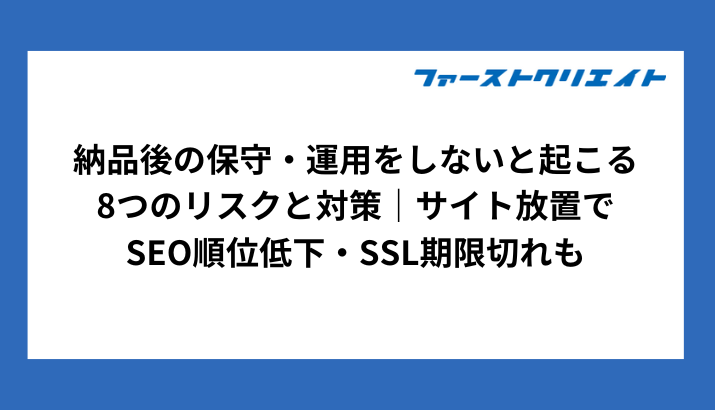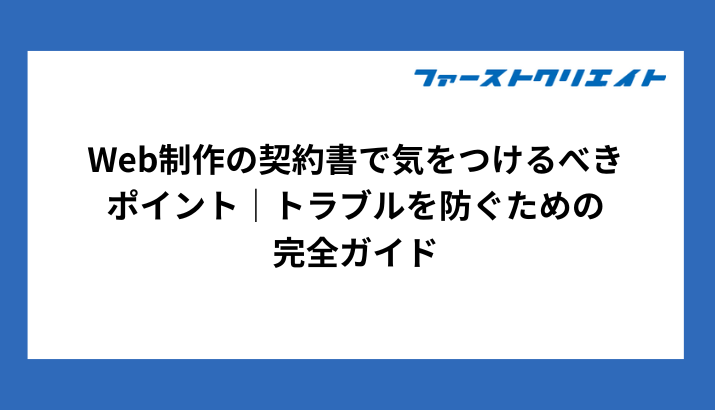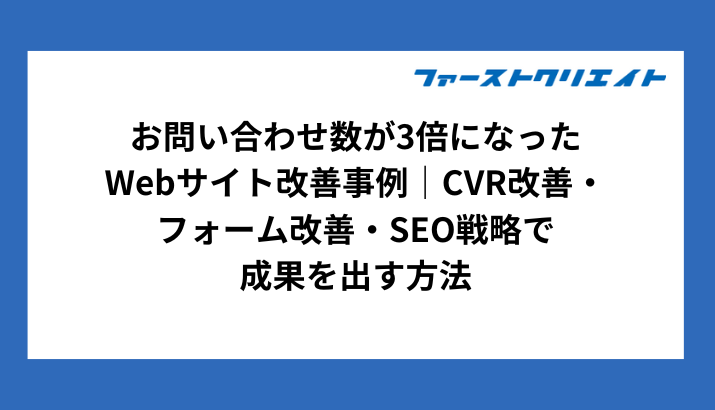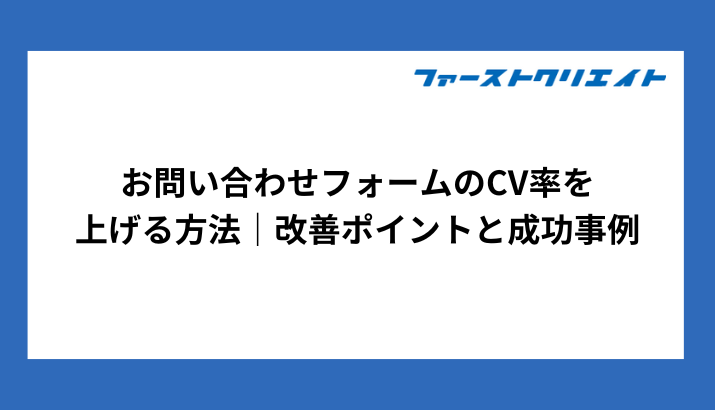ブログは毎日更新しないとダメ?更新頻度とSEO・集客の関係を解説
2025年10月3日
Web制作の契約書で気をつけるべきポイント|トラブルを防ぐための完全ガイド
2025年10月18日・納品後の保守や運用って本当に必要なのだろうか
・更新を止めても特に問題はないのでは?
そんな疑問を持つ担当者様も多いのではないでしょうか。
実は、Webサイトの「納品後 保守 運用」を怠ると、SEO順位の低下や表示崩れ、SSL証明書切れなど、多くのトラブルが発生します。放置してしまうことで、ブランドの信頼や集客にも悪影響を与えてしまうのです。
この記事では、名古屋のWeb制作会社が、保守・運用をしないことで起こる具体的なリスクや費用面の損失、そして正しい運用体制の作り方をわかりやすく解説します。読むことで、なぜ保守・運用が“サイトを守る鍵”なのかが理解できます。ぜひ最後までお読みください。
納品後の保守・運用をしないとどうなるか|結論と全体像
Webサイトの納品は「完成」ではなく「スタート」です。名古屋の多くの企業がWeb制作会社に依頼してサイトを公開しますが、その後の保守・運用を行わないことでさまざまな問題を招いています。制作直後は問題がなくても、時間の経過とともにトラブルが発生するのが実際の現場です。納品後の運用を怠ると、サイトの品質・安全性・集客力のすべてが低下し、最終的には顧客の信頼を失う結果になります。
例えば、フォームの不具合や表示の乱れ、サーバー証明書の期限切れ、SEO評価の低下などが起きやすくなります。これらの問題は、定期的な点検や更新をしていれば防げるものばかりです。企業のWeb担当者が「公開したから安心」と考えて放置してしまうと、見えない部分で劣化が進行し、修復コストが膨らむケースも多くあります。
つまり、Webサイトを長期的に活用して成果を出すためには、制作と同じくらい「運用フェーズ」が重要です。名古屋のWeb制作会社の多くも、納品後の保守契約を推奨しています。それは単なる追加サービスではなく、企業のデジタル資産を守り続けるための基本的な取り組みだからです。
納品後の保守・運用は、トラブルを防ぐための保険ではなく、Webサイトの価値を維持・成長させるための「投資」です。
「納品=完成」ではない理由(運用で価値が生まれる)
Webサイトは公開して終わりではなく、公開後に改善を続けることで初めて効果を発揮します。理由は、インターネット環境やユーザーの行動、検索エンジンのアルゴリズムが常に変化しているためです。納品直後に最適化されていた設計でも、数か月後には古くなることがあります。
たとえば以下のような変化が日常的に起きています。
- Googleの検索評価基準(アルゴリズム)の更新
- スマートフォンOSやブラウザの仕様変更
- ユーザーの検索キーワードや行動傾向の変化
これらに対応できないまま放置すると、サイトの表示崩れやSEO順位の低下、コンバージョン率の悪化を招きます。つまり「納品=完成」ではなく、公開後の分析と改善によって価値が生まれるのです。
実際、名古屋のWeb制作会社の中には、運用を前提とした設計を行う企業が増えています。定期的なアクセス解析や改善提案を行い、クライアントと二人三脚で成果を伸ばしていく形が主流になりつつあります。継続的な運用を行うことが、Webサイトを「作っただけのもの」から「成果を出す資産」に変える唯一の方法です。
放置によって起きる代表的なトラブルの俯瞰
保守・運用を行わずWebサイトを放置すると、表面上は動いていても内部では多くの問題が発生します。代表的なトラブルは次のとおりです。
- SSL証明書の期限切れによる「安全でないサイト」警告
- 問い合わせフォームや予約機能の不具合
- CMSやプラグインの更新不足による脆弱性
- 画像容量の肥大化による表示速度の低下
- 古い情報のまま放置による信頼性の低下
これらの問題は一度に表面化するのではなく、少しずつ積み重なっていきます。結果としてユーザー離れが進み、検索順位が下がり、集客効果が失われます。名古屋の企業の中でも、こうしたトラブルをきっかけにサイト全体をリニューアルするケースが多く見られます。
Webサイトの放置は、建物のメンテナンスを怠るのと同じで、気づいた時には手遅れになっていることが多いです。そのため、納品後も継続的な保守と運用を行い、健全な状態を維持することが非常に重要です。
【即時〜短期】保守・運用をしないことで起きる初期トラブル
Webサイトを納品後に放置すると、最初に現れるのは「小さな不具合」です。名古屋の企業がWeb制作会社に依頼してサイトを公開しても、運用を止めると短期間で見えない部分にエラーが発生します。これらは初期段階であればすぐに修正できますが、放置すると大きな障害に発展します。納品直後の安定期こそ、継続的な点検が欠かせません。
フォーム不達・決済不具合・表示崩れの見逃し
サイト公開後すぐに起こるトラブルの多くは、見た目には気づきにくいものです。代表的な例として、問い合わせフォームの送信エラーや、決済システムの不具合、スマートフォンでの表示崩れがあります。これらは運用中の監視がなければ発見が遅れ、顧客との接点を失う原因になります。
- フォームの送信先メールアドレス変更に気づかない
- 決済プラグインやAPI仕様の変更でエラーが発生
- ブラウザ更新によるデザイン崩れ
このような不具合を放置すると、問い合わせや注文が来ない状態が続き、機会損失が拡大します。名古屋のWeb制作会社では、納品後の1〜3か月を「安定稼働期間」として細かくチェックするケースが一般的です。公開後の見えない不具合を早期に発見・修正することが、信頼を守る第一歩です。
ドメイン/サーバー/SSLの期限切れによる表示停止
次に多いトラブルが「契約関連の期限切れ」です。ドメイン(サイトの住所)やサーバー(サイトの保管場所)、SSL証明書(通信を暗号化する仕組み)は、有効期限を過ぎると自動的にサイトが停止します。特にSSLが切れると、ブラウザに「安全でない接続」と警告が出て、ユーザーが離れてしまいます。
- ドメイン更新忘れでサイトが404エラーになる
- サーバー契約の支払い遅延で強制停止
- SSL更新漏れによるセキュリティ警告表示
これらのトラブルは一度発生すると復旧に時間がかかり、検索エンジンの評価にも悪影響を与えます。たとえば、サイトが数日間閲覧できなくなるだけでインデックスが削除されることもあります。名古屋のWeb制作会社では、更新期限の管理を含む保守契約を標準化している企業も多く、契約情報を一元管理して定期確認する仕組みが、トラブル防止の鍵です。
バックアップ未設定によるデータ消失
最後に見逃せないのが「バックアップ未設定によるデータ消失」です。サーバー障害や人為的ミス、システム更新時のエラーによって、サイト全体が消えてしまうことがあります。バックアップとは、データを複製して安全な場所に保存しておく仕組みのことです。
- CMS更新中のエラーで全データが初期化
- 誤ってファイル削除し、復元できない
- サーバー障害でデータベースが破損
バックアップを取っていない場合、最悪のケースでは再構築に数十万円の費用と数週間の時間が必要です。名古屋のWeb制作会社では、毎日または週単位で自動バックアップを設定し、複数の世代を保存するのが一般的です。データを守る仕組みを最初に整えることが、すべてのリスク対策の出発点です。
【中期】機能劣化と機会損失|更新しないデメリット
Webサイトを公開した後も、環境や技術は日々変化しています。名古屋の企業がWeb制作会社に依頼して作成したサイトでも、更新を怠ると中期的な機能劣化が進みます。見た目に問題がなくても内部では互換性不良や速度低下、情報の古さなどが重なり、ユーザー体験が損なわれていきます。更新を止めることは、時間をかけて信頼を削る行為といえます。
CMS・プラグイン未更新での互換性不良・不具合連鎖
WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)やプラグインを更新しないと、互換性の問題が起こります。CMSとは、専門知識がなくてもWebサイトを管理・更新できる仕組みのことです。開発元は常にバグ修正や機能改善を行っていますが、古いまま放置すると最新環境に対応できず、サイトが正常に動作しなくなる危険があります。
- 古いプラグインが新しいPHPバージョンで動かない
- 更新していないテーマがレイアウト崩れを引き起こす
- 不具合の修正が適用されず脆弱性が残る
このような状態が続くと、ページ表示の乱れや機能停止が連鎖的に起こります。結果として、修復コストが増加し、復旧までに時間がかかります。名古屋のWeb制作会社でも、更新を怠った結果として再構築を余儀なくされた事例が少なくありません。CMSやプラグインの更新は、安定稼働を守る最低限のメンテナンスです。
表示速度低下と離脱率上昇(画像最適化・キャッシュ未運用)
更新を行わないと、サイトの表示速度が徐々に遅くなります。画像や動画などのデータが増えると容量が重くなり、ユーザーがページを開くまでに時間がかかります。また、キャッシュ(データを一時的に保存して再利用する仕組み)が適切に設定されていないと、毎回の読み込み負担が大きくなります。
- 画像サイズの最適化が行われていない
- 不要なスクリプトやプラグインが残っている
- キャッシュ設定が不十分で読み込みに時間がかかる
このような問題が積み重なると、ユーザーが途中で離脱し、検索エンジンの評価も下がります。特にスマートフォンでの閲覧では、読み込みに3秒以上かかると半数以上が離脱するといわれています。名古屋の企業にとっても、地元ユーザーの体感速度は集客に直結します。定期的な最適化は、見た目以上にユーザー満足度とCV(成果)を左右する要素です。
コンテンツ未更新によるCVR低下・LPO未実施の機会損失
サイトの情報を更新しないと、内容が古くなり信頼性が落ちます。検索エンジンは「新しい情報」を好むため、更新が止まったサイトは評価が下がりやすくなります。さらに、LPO(ランディングページ最適化)を行わないと、訪問者が問い合わせや購入につながらないまま離脱してしまいます。
- 掲載事例や価格が古く、信頼を失う
- ユーザーの検索ニーズと内容が合わなくなる
- フォーム導線やボタン配置の改善が行われない
これらの放置はCVR(コンバージョン率)の低下につながります。実際に、定期的に更新を行う名古屋のWeb制作会社のクライアントでは、改善後に平均20〜30%の成果向上が見られるケースもあります。コンテンツを育てることは、企業の信頼と成果を継続的に伸ばす最も確実な方法です。
【長期】セキュリティ・ブランド・法令面の重大リスク
保守・運用をしない状態が長期化すると、最も深刻なリスクが「セキュリティ」「ブランド」「法令遵守」に関するものです。名古屋の企業がWeb制作会社に依頼して構築したサイトでも、定期点検を怠ると安全性が低下し、信用を大きく損なう事態に発展します。これらのリスクは、短期間では表面化しませんが、一度起こると取り返しがつかない損失を生みます。
脆弱性放置による改ざん・マルウェア・情報漏えい
Webサイトのシステムは常に外部からの攻撃にさらされています。脆弱性(ぜいじゃくせい)とは、悪意のある第三者が攻撃に利用できるシステムの弱点のことです。CMSやプラグインを更新しないまま放置すると、この脆弱性を突かれて改ざんや情報漏えいが発生します。
- トップページに不正な広告やスパムリンクが埋め込まれる
- フォーム経由で個人情報が流出する
- マルウェア感染で訪問者にも被害が及ぶ
このような被害は、企業サイトで起きれば信頼を失うだけでなく、顧客からの損害賠償請求につながる可能性もあります。特に中小企業では、セキュリティ担当者がいないため発見が遅れ、被害が長期間続くケースがあります。名古屋のWeb制作会社でも、保守契約を結んでいなかった企業が感染被害を受け、復旧に数週間を要した例が報告されています。セキュリティ対策は「攻撃されてから」ではなく「攻撃されないようにする」ことが最も重要です。
風評被害と検索結果での警告表示(信頼失墜)
セキュリティ事故や改ざんが発生すると、検索エンジンが自動的に警告を出すことがあります。Googleでは感染の疑いがあるサイトに「このサイトは安全ではありません」と赤い警告表示を付けます。この状態になると、ユーザーのアクセスは激減し、検索順位も大きく下がります。
- Google検索結果に警告マークが表示される
- SNSや口コミサイトで「危険なサイト」と拡散される
- 顧客や取引先の信頼を失う
こうした風評被害は、一度発生すると修復に長い時間がかかります。企業ブランドを回復するには、再審査申請や再構築、そして新しいドメイン取得が必要になる場合もあります。名古屋地域では、観光業や店舗系のサイトがこうした被害を受けると、実店舗の集客にも影響が出るケースがあります。Webサイトの安全性は、そのまま企業の信用を守る「看板」となります。
クッキー同意/個人情報保護/表示義務の未対応による法令リスク
近年では、サイト運用において法令対応も欠かせません。クッキー(Cookie)とは、訪問者の行動データを保存する仕組みで、分析や広告配信に使われます。これらを使用する際には、ユーザーに対して目的を明示し、同意を得ることが義務づけられています。また、個人情報保護法や特定商取引法に基づく表示も必要です。
- クッキー使用の明示と同意管理の未実施
- 個人情報の取り扱い方針が古いまま
- 会社情報や問い合わせ先の不備による行政指導
法改正は定期的に行われており、対応しないままでは罰則を受ける可能性もあります。特に、海外アクセスを想定する企業では、GDPR(EU一般データ保護規則)など国際的なルールにも注意が必要です。名古屋のWeb制作会社では、最新の法令に基づいて定期的にプライバシーポリシーを更新するサポートを行う企業も増えています。法令対応を怠ることは、企業の信頼だけでなく事業継続にも影響を及ぼす重大なリスクです。
SEOへの影響|保守・運用をしないと検索順位はどうなるか
Webサイトの保守・運用を怠ると、SEO(検索エンジン最適化)の効果が徐々に失われます。SEOとは、検索エンジン上で自社のサイトを上位に表示させるための施策のことです。検索エンジンは常に最新の情報と技術に基づいて評価を行うため、放置されたサイトは自然と順位を下げていきます。名古屋の企業にとっても、Web制作会社に依頼して構築したサイトを維持することは、集客や信頼を守る上で欠かせません。更新されないサイトは、競合の継続的な最適化に負けて順位を落とし、見られなくなるリスクが高まります。
クロールエラー・リンク切れ・構造化データ崩れの蓄積
検索エンジンは「クローラー」と呼ばれるプログラムを使ってWebサイトを巡回し、内容を評価しています。この過程でエラーが増えると、正しく情報が伝わらず順位が下がります。クロールエラーとは、ページが削除・変更されて正しく読み取れない状態のことです。また、リンク切れや構造化データの崩れも評価を下げる要因になります。
- URLの変更や削除による404エラー
- 外部リンクの消滅やリダイレクト設定ミス
- 構造化データ(検索結果での表示情報)タグの不整合
これらのエラーは、保守運用をしていれば早期に修正できますが、放置すると検索エンジンが「品質が低いサイト」と判断します。結果としてクロール頻度が下がり、新しい情報も評価されにくくなります。名古屋のWeb制作会社でも、月次でクローラビリティを確認し、リンク整備を行うサポートを提供する企業が多くあります。リンクと構造の健全性を保つことは、SEOの土台を守る基本です。
コアウェブバイタル未改善が招く評価低下
Googleは近年、ユーザー体験を重視する評価指標として「コアウェブバイタル(Core Web Vitals)」を導入しました。これはページの読み込み速度や操作のスムーズさ、表示の安定性などを数値化したものです。更新や最適化を行わないサイトは、これらの指標が悪化しやすくなります。
- 画像や動画の容量が大きく読み込みが遅い
- スクリプトやプラグインが多く動作が重い
- レイアウトのズレでクリックミスが発生
これらの問題はユーザーの満足度を下げるだけでなく、Googleの評価にも直接影響します。特にモバイル検索では、コアウェブバイタルのスコアが悪いと上位表示が難しくなります。名古屋のWeb制作会社では、定期的な速度計測と改善レポートを実施する企業も多く、ローディング改善をSEOの一環として行っています。ユーザー体験を継続的に向上させることが、SEO評価の維持に直結します。
競合の定期最適化に置き去りにされるメカニズム
SEOは「相対評価」で決まるため、自社が何もしていなくても、他社が改善を続ければ順位が下がります。たとえ納品時に最適化されていても、競合がコンテンツ更新や内部施策を重ねていけば、相対的に評価が落ちていく仕組みです。
- 競合が新しいキーワードで記事を増やす
- 内部リンク構造を改善し評価を高める
- ユーザー行動データを分析しUXを向上させる
こうした競合の努力に対抗するには、継続的なデータ分析と更新が不可欠です。名古屋の企業が地域SEOで上位を維持しているケースの多くは、定期的にコンテンツを見直し、内部リンクやメタ情報を調整している企業です。保守・運用を止めるということは、競合に順位を明け渡すことと同義です。継続的な改善こそが、検索上位を守る唯一の戦略です。
数字で見る損失|想定コストとリカバリー費用比較
Webサイトの保守・運用をしないことで発生する損失は、金額に換算すると想像以上に大きくなります。名古屋の企業でも「コスト削減のために保守を外した」結果、トラブル対応で倍以上の費用が発生するケースが少なくありません。保守費用を節約したつもりが、実際には「高くつく選択」になることが多いのです。
放置→障害→復旧の緊急対応費と機会損失
保守・運用を行わないまま放置すると、ある日突然サイトが表示されなくなったり、問い合わせが届かなくなったりします。トラブル発生後に緊急で対応を依頼すると、通常の保守費用よりも高額な復旧コストがかかります。
- SSL切れやサーバー障害による緊急復旧:10〜30万円
- マルウェア感染や改ざん対応:20〜50万円
- データ消失からの再構築:30〜100万円以上
これらは実際に名古屋のWeb制作会社でも報告されている相場です。復旧作業中はサイトが停止するため、その期間に発生する「問い合わせ・予約・売上」の機会損失も加わります。仮に1日あたりの売上が5万円の場合、3日間の停止で15万円の損失です。予防的な運用をしていれば防げた損失を後から取り戻すのは、非常に難しいのが現実です。
月額保守費用との比較(トータルコストでの合理性)
月額の保守・運用契約は、一般的に1〜3万円程度で提供されています。一見すると毎月の固定費に感じますが、年間を通して考えると非常に合理的な費用です。トラブルが起きた場合の復旧コストと比較すると、その差は歴然です。
| 項目 | 保守契約あり | 保守契約なし |
|---|---|---|
| 月額費用 | 約2万円 | 0円 |
| 年間コスト | 約24万円 | 0円 |
| 障害発生時の対応費 | 0〜5万円(軽微) | 30〜80万円(緊急対応) |
| ダウン期間の損失 | 最短数時間 | 数日〜1週間 |
このように、保守費用は「トラブルが起きたときの保険料」のようなものです。さらに、保守契約にはアクセス分析や軽微な更新作業が含まれる場合もあり、サイトを最新状態に保てるという付加価値もあります。長期的に見れば、保守費用は支出ではなく「資産を守るための投資」です。
社内工数の隠れコスト(担当者の属人化リスク)
保守・運用を外部に委託せず社内対応に任せる場合、担当者の負担や属人化のリスクも見逃せません。担当者が退職・異動した場合、設定情報や手順が引き継がれず、トラブル対応ができなくなるケースが多くあります。
- サーバーやドメイン情報の管理者が1人しかいない
- 更新手順が文書化されていない
- 担当者の不在時に障害対応が遅れる
こうした属人化は、見えない「隠れコスト」を発生させます。担当者の時間単価を仮に1時間3,000円とすると、トラブル対応で10時間費やせば3万円の人件費が発生します。さらに精神的な負担や他業務の遅延も加わり、結果的に企業全体の生産性を下げます。名古屋の中小企業でも、保守体制を外注化してトラブル対応の標準化を図る例が増えています。属人化を防ぎ、安定運用を維持するためには、保守契約による専門管理が最も効率的です。
具体例|保守・運用をしないと起きたケーススタディ
保守・運用を怠ったことで起きたトラブルは、数字だけでなく実際の被害としても大きな影響を及ぼします。名古屋の企業においても、「更新を止めた数か月後」に問題が表面化するケースが多く見られます。ここでは、保守をしなかったことで発生した典型的な3つの事例を紹介します。いずれも、日々の運用と管理を行っていれば防げたものばかりです。
SSL失効で広告停止・CV喪失になった事例
ある名古屋の企業では、SSL証明書の更新を忘れたことでサイトが「安全ではありません」と表示され、広告配信が自動停止になりました。SSLとは、サイトと利用者の通信を暗号化し安全性を保つ仕組みのことです。証明書の有効期限は通常1年で、期限が切れるとブラウザが警告を出します。
- Google広告の審査で「安全でないサイト」と判断され停止
- フォーム送信率が激減し、CV(コンバージョン)が90%減少
- 証明書更新と広告再審査に2週間を要した
結果として、広告経由の問い合わせや売上が止まり、再開までに大きな損失を出しました。SSL更新は数分で終わる作業ですが、保守契約がなければ誰も気づきません。たった一つの更新忘れが、信頼と収益を同時に失う結果を招きます。
プラグイン脆弱性からの改ざん→検索除外の事例
別の中小企業では、WordPressのプラグイン更新を放置していたことで、外部からの攻撃を受けました。サイトが改ざんされ、知らないうちにスパムサイトへのリンクが埋め込まれた結果、Googleの検索結果から除外(インデックス削除)されました。
- 古いプラグインの脆弱性を悪用されて侵入
- HTMLソースに大量の不正リンクを挿入
- 検索結果で「このサイトは危険です」と警告表示
修復のために専門業者へ依頼し、復旧費用に40万円以上を要しました。検索順位の回復にも約3か月かかり、その間に顧客流入が大幅に減少しました。名古屋のWeb制作会社では、このようなリスクを防ぐために脆弱性情報を常時監視し、プラグインを最新に保つサービスを提供しています。更新を止めることは、攻撃者に扉を開けているのと同じ行為です。
バックアップ未実施で復旧不可になった事例
最後に紹介するのは、バックアップを取っていなかったために復旧できなくなったケースです。あるイベント運営会社のサイトでは、担当者が誤ってサーバー上のファイルを削除してしまい、データが完全に消失しました。バックアップとは、データのコピーを別の場所に保存しておく仕組みです。
- 手動でのバックアップを数か月行っていなかった
- サーバー業者側にも自動保存設定がなかった
- 過去のデザイン・画像・記事がすべて消失
結果的にサイトをゼロから再構築することになり、制作費用として約70万円、納期は1か月以上かかりました。復旧期間中はイベントの告知もできず、集客にも影響しました。名古屋のWeb制作会社では、1日1回の自動バックアップを推奨し、クラウド保存で二重保護を行う体制を整えています。バックアップの未設定は、最悪の場合「会社の情報資産の喪失」を意味します。
具体例|保守・運用をしないと起きたケーススタディ
保守・運用を怠ったことで起きたトラブルは、数字だけでなく実際の被害としても大きな影響を及ぼします。名古屋の企業においても、「更新を止めた数か月後」に問題が表面化するケースが多く見られます。ここでは、保守をしなかったことで発生した典型的な3つの事例を紹介します。いずれも、日々の運用と管理を行っていれば防げたものばかりです。
SSL失効で広告停止・CV喪失になった事例
ある名古屋の企業では、SSL証明書の更新を忘れたことでサイトが「安全ではありません」と表示され、広告配信が自動停止になりました。SSLとは、サイトと利用者の通信を暗号化し安全性を保つ仕組みのことです。証明書の有効期限は通常1年で、期限が切れるとブラウザが警告を出します。
- Google広告の審査で「安全でないサイト」と判断され停止
- フォーム送信率が激減し、CV(コンバージョン)が90%減少
- 証明書更新と広告再審査に2週間を要した
結果として、広告経由の問い合わせや売上が止まり、再開までに大きな損失を出しました。SSL更新は数分で終わる作業ですが、保守契約がなければ誰も気づきません。たった一つの更新忘れが、信頼と収益を同時に失う結果を招きます。
プラグイン脆弱性からの改ざん→検索除外の事例
別の中小企業では、WordPressのプラグイン更新を放置していたことで、外部からの攻撃を受けました。サイトが改ざんされ、知らないうちにスパムサイトへのリンクが埋め込まれた結果、Googleの検索結果から除外(インデックス削除)されました。
- 古いプラグインの脆弱性を悪用されて侵入
- HTMLソースに大量の不正リンクを挿入
- 検索結果で「このサイトは危険です」と警告表示
修復のために専門業者へ依頼し、復旧費用に40万円以上を要しました。検索順位の回復にも約3か月かかり、その間に顧客流入が大幅に減少しました。名古屋のWeb制作会社では、このようなリスクを防ぐために脆弱性情報を常時監視し、プラグインを最新に保つサービスを提供しています。更新を止めることは、攻撃者に扉を開けているのと同じ行為です。
バックアップ未実施で復旧不可になった事例
最後に紹介するのは、バックアップを取っていなかったために復旧できなくなったケースです。あるイベント運営会社のサイトでは、担当者が誤ってサーバー上のファイルを削除してしまい、データが完全に消失しました。バックアップとは、データのコピーを別の場所に保存しておく仕組みです。
- 手動でのバックアップを数か月行っていなかった
- サーバー業者側にも自動保存設定がなかった
- 過去のデザイン・画像・記事がすべて消失
結果的にサイトをゼロから再構築することになり、制作費用として約70万円、納期は1か月以上かかりました。復旧期間中はイベントの告知もできず、集客にも影響しました。名古屋のWeb制作会社では、1日1回の自動バックアップを推奨し、クラウド保存で二重保護を行う体制を整えています。バックアップの未設定は、最悪の場合「会社の情報資産の喪失」を意味します。
まとめ|「納品後の保守・運用」を前提にした成功設計へ
Webサイトの価値は、納品の瞬間ではなく「納品後の運用」によって決まります。名古屋の企業がWeb制作会社へ依頼する際も、デザインや機能だけでなく、その後の保守・運用体制を含めた設計を行うことが成功の鍵です。Webサイトは作って終わりではなく、育てることで成果を最大化できる長期的な資産です。
初期設計から運用コストを織り込む
多くの企業が「制作費」と「運用費」を別物として考えがちですが、本来は一体のものです。初期段階から運用フェーズを見据えた設計を行うことで、後々の保守コストやトラブルを大幅に減らすことができます。
- 更新や修正がしやすい構造に設計する
- プラグインや外部サービスを最小限にする
- 担当者が操作しやすい管理画面を整える
これらを意識するだけでも、日々の運用負担が軽減されます。名古屋のWeb制作会社では、設計段階から運用手順書を用意し、クライアントが自走できる仕組みを提供する企業も増えています。初期設計で「更新しやすさ」を考慮することが、長期的な安定運用を支える最良の投資です。
KPIとSLAで「守る運用」から「育てる運用」へ
保守・運用を単なる「維持作業」と捉えるのではなく、「成長戦略の一部」として設計することが重要です。そのためには、KPI(重要業績評価指標)とSLA(サービス品質保証)を設定し、数値で運用を管理します。
- KPI:問い合わせ件数、滞在時間、CVRなど成果指標を定義
- SLA:障害発生時の対応時間や稼働率の目標を設定
- 定期レポート:改善提案や施策結果を可視化
このような仕組みを導入することで、運用が「守るだけ」ではなく「成果を育てる」段階へ進化します。名古屋の企業では、Web制作会社と定例ミーティングを行い、データ分析を基に改善を繰り返すスタイルが定着しつつあります。継続的な保守・運用は、サイトを安定させるだけでなく、事業を成長させるための戦略的パートナーシップです。
ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webのことは全然わからないので、一からしっかり説明してくれるWeb制作会社を探している」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。