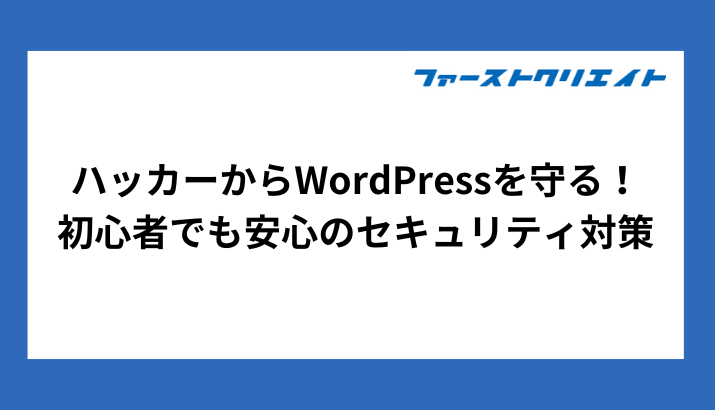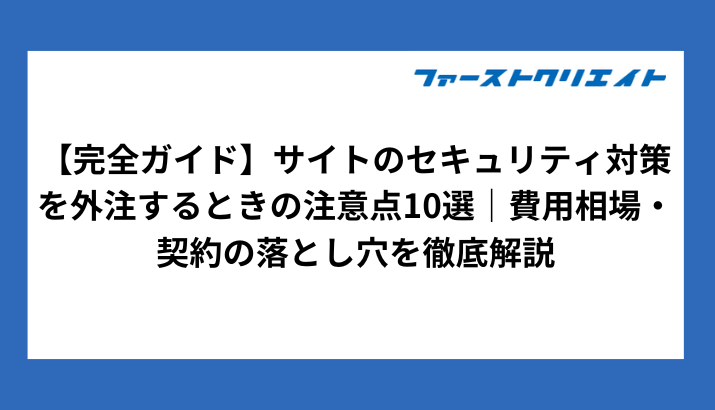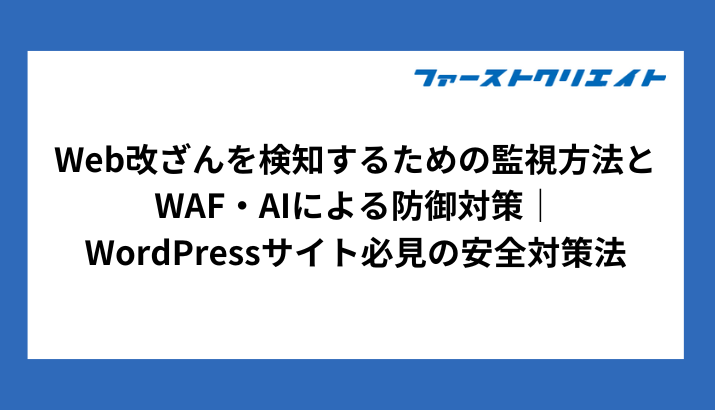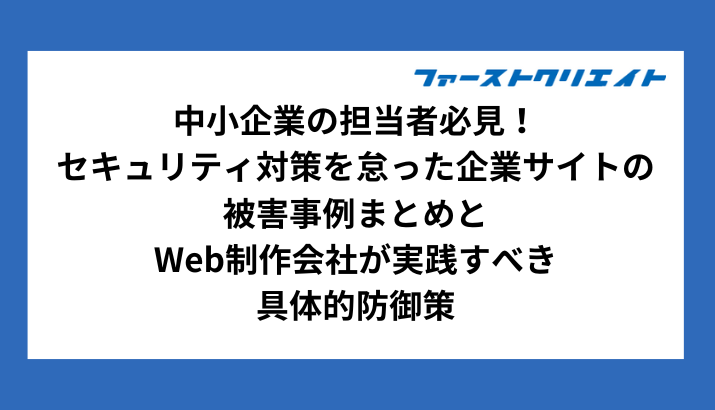今すぐ実践!WordPressの脆弱性を簡単にチェックする方法まとめ
2025年5月9日
クロスサイトスクリプティング(XSS)とは?対策方法を解説
2025年5月9日「WordPressがハッカーに狙われやすいのはなぜ?」「どんな攻撃をされるのか分からない」
そんな不安や疑問を感じていませんか?
WordPressは世界中で利用されているため、ハッカーにとって格好の標的です。適切な対策をしていなければ、サイトの乗っ取りや情報流出など深刻な被害につながるおそれがあります。
そこで本記事では、WordPressサイトの運営者に向けて、ハッカーの代表的な手口や実際の被害事例、防ぎ方、信頼できるセキュリティプラグインについて分かりやすく解説します。自分のサイトを守るために、ぜひ最後までご覧ください。
WordPressがハッカーに狙われやすい理由とは?
WordPressは非常に便利なホームページ作成ツールですが、実はハッカーの攻撃対象になりやすいという特徴があります。理由は1つではなく、複数の要因が関係しています。以下では、その具体的な理由を3つに分けて詳しく解説します。
世界中で使われているため攻撃対象になりやすい
WordPressは全世界で多くの人が使っている人気のホームページ作成ソフトです。
人気があるということは、それだけ使っている人が多く、ハッカーにとって攻撃の対象が多いことを意味します。
実際に、世界中のホームページのうち4つに1つ以上がWordPressで作られているといわれています。
攻撃対象が多ければ、同じ方法でたくさんのサイトに侵入できる可能性が高くなります。
つまり、利用者が多いWordPressはハッカーにとって「効率よく攻撃できる標的」であるといえます。
管理が甘いサイトが多くハッカーにとって効率が良い
WordPressは簡単に始められるという魅力がありますが、それが裏目に出ることもあります。
セキュリティの知識がなくても始められるため、管理が甘くなりやすいのです。
例えば以下のようなことが原因になります。
- 初期設定のまま使い続ける
- 弱いパスワードを使う
- 古いプラグインやテーマを放置する
これらの状態では、ハッカーが自動でサイトを探し、簡単に侵入できてしまいます。
ハッカーにとっては「対策が甘いサイト」はまさに入り口が開いたままの家のような存在です。
オープンソースゆえに脆弱性が見つかりやすい
WordPressは「オープンソース」と呼ばれる形式で作られています。
オープンソースとは、だれでも中身を見ることができるソフトウェアのことです。
これにより開発者が自由に機能を追加できる一方で、悪意のある人もプログラムの弱点を見つけやすくなります。
ハッカーはその弱点(=脆弱性)を見つけ、攻撃に利用することがあります。
特に更新されていないプラグインやテーマに弱点が残っていると、そこから侵入されるおそれが高まります。
オープンソースであるWordPressは、自由度が高い反面、セキュリティ面での注意が必要な仕組みです。
実際にあったWordPressサイトへのハッキング手口と事例
WordPressサイトへのハッキングは現実に多く発生しています。ここでは、代表的な5つの手口と実際に起きた被害の例を紹介します。自分のサイトが狙われないように、どのような手法があるのかを理解しておくことが重要です。
不正ログイン(ブルートフォース攻撃)
ブルートフォース攻撃とは、ログインIDとパスワードの組み合わせを何度も自動で試して不正に侵入する方法です。
この攻撃は特に、短くて単純なパスワードを使っているサイトが狙われます。
例えば「123456」や「password」など、よく使われるパスワードは一瞬で突破されます。
ある中小企業のブログサイトでは、管理者のIDを「admin」、パスワードを「test123」にしていたため、2時間以内に突破され、サイト全体が乗っ取られた事例があります。
単純なパスワードを使っていると、ハッカーにとってはドアの鍵がかかっていないのと同じです。
プラグイン・テーマの脆弱性を悪用
プラグインやテーマには便利な機能が多く含まれていますが、古いバージョンには弱点(=脆弱性)が残っていることがあります。
ハッカーはその弱点を見つけて、サイトに侵入したり、情報を盗んだりします。
特に人気のプラグイン「Contact Form 7」や「Slider Revolution」では、過去に大規模な脆弱性が見つかり、多くのサイトが影響を受けました。
実際に、美容院の予約サイトが古いスライダー機能を使っていたことで、そこから悪意のあるコードを埋め込まれ、検索結果に不正な広告が表示されてしまった例もあります。
プラグインやテーマを更新しないことは、玄関のカギを古いままにしておくのと同じくらい危険です。
SQLインジェクションによるデータベース攻撃
SQLインジェクションとは、入力欄に特殊な命令文(SQL)を入れることで、データベースを不正に操作する攻撃です。
この攻撃は、ログインフォームや検索ボックスなどで入力チェックが不十分なときに起きやすくなります。
ある情報発信ブログでは、検索フォームに「’ OR ‘1’=’1」などの命令を入れられたことで、ユーザー情報が外部に漏れてしまいました。
この攻撃により、名前・メールアドレス・購入履歴などのデータが盗まれる危険性があります。
フォームの設計が甘いだけで、サイト全体の情報が流出する可能性があります。
マルウェアやバックドアの埋め込み
マルウェアとは、悪意のあるプログラムのことで、WordPressサイトにこっそり埋め込まれることがあります。
バックドアは、管理者に気づかれずに再侵入できる仕組みです。
実際に、ニュースメディアサイトにマルウェアが埋め込まれ、ページを開いたユーザーのパソコンが自動で不正ソフトをダウンロードしてしまう事件が発生しました。
このような攻撃は、サイトを訪れた人にも被害を及ぼすため、信頼を大きく失います。
一度でもマルウェアを入れられると、運営者だけでなく読者にも大きな被害が出ます。
ファイルアップロード機能を悪用した改ざん
画像や書類などをアップロードできる機能は便利ですが、セキュリティ対策が甘いとハッカーに悪用されます。
特に、アップロードされたファイルの種類や中身をチェックしない設定だと危険です。
あるイベントサイトでは、アップロード機能を通じて「.php」ファイルが送られ、サーバー内に悪意のあるコードが実行されました。
その結果、サイトが改ざんされ、表示内容が全く関係のない広告やウイルス配布ページに変わってしまいました。
アップロード機能は便利な反面、入り口として悪用されることが多いポイントです。
WordPressサイトを守るために今すぐできる基本対策
WordPressを安全に使い続けるためには、日ごろからの基本的な対策が欠かせません。ハッカーの攻撃からサイトを守るためには、特別な知識や技術がなくてもできることがたくさんあります。ここでは、すぐに始められる4つの基本対策を紹介します。
管理画面URLの変更で攻撃を回避する
WordPressのログイン画面は「/wp-admin」や「/wp-login.php」というURLで知られています。
この初期設定のままだと、ハッカーが簡単にログイン画面にたどり着きます。
特にブルートフォース攻撃(パスワードを何度も試す攻撃)に対して無防備になります。
「WPS Hide Login」などのプラグインを使えば、ログイン画面のURLを変更できます。
たとえば「/mylogin123」のように独自のURLにすれば、外部からの攻撃を受けにくくなります。
管理画面の入り口を変えることで、ハッカーの自動攻撃を防ぐ第一歩になります。
強固なパスワードと2段階認証の導入
弱いパスワードを使っていると、簡単にログインされてしまいます。
「abc123」や「password」といった単純なパスワードは避けましょう。
以下の条件をすべて満たすパスワードが理想です。
- 英語の大文字と小文字を組み合わせる
- 数字と記号を含める
- 12文字以上にする
また、「Google Authenticator」などを使って2段階認証を追加すれば、安全性がさらに高まります。
ログイン時にスマートフォンでの確認が必要になるため、不正アクセスのリスクを大きく減らせます。
パスワードと2段階認証の組み合わせで、ログインの壁を強固にしましょう。
プラグイン・テーマ・本体の最新版維持
古いバージョンには、知られている弱点(脆弱性)が残っている可能性があります。
ハッカーはその情報をもとに、攻撃の入り口を探してきます。
WordPress本体、プラグイン、テーマのいずれも最新の状態に保ちましょう。
特に以下のような状態は危険です。
- 何年も更新されていないテーマを使用
- 使用していないプラグインを放置
- 自動更新が無効になっている
管理画面にログインすれば、更新の有無をすぐに確認できます。
「最新版を使う」だけで、防げる攻撃が数多くあります。
信頼性のあるプラグイン・テーマだけを使用する
見た目や機能が便利なプラグインやテーマでも、信頼できないものを使うと危険です。
悪意のあるコードが含まれていることがあり、知らない間にサイトが乗っ取られるおそれがあります。
以下のポイントをチェックしましょう。
- 公式ディレクトリに登録されているか
- 最終更新日が最近か
- レビューやダウンロード数が多いか
無料でも安全なものはたくさんありますが、出どころの不明なテーマや配布サイトからの入手は避けてください。
信頼できる制作者が提供するプラグインとテーマだけを使うことが、サイトの安全を守る基本です。
専門知識不要!おすすめのWordPressセキュリティプラグイン5選
セキュリティ対策は難しいと思われがちですが、WordPressではプラグインを使えば、専門知識がなくてもサイトを守れます。ここでは、初心者にも使いやすく信頼できるセキュリティプラグインを5つ紹介します。用途や特徴を比較しながら、自分のサイトに合ったものを選びましょう。
Wordfence Security – 総合的な防御対策
Wordfence Securityは、世界中で利用されている人気のセキュリティプラグインです。
ファイアウォール(防御壁)とマルウェアスキャン機能を備えており、外部からの不正アクセスやウイルスをブロックできます。
管理画面も日本語に対応しており、使いやすさも魅力です。
実際に、多くの企業サイトでも導入されており、高い評価を得ています。
セキュリティ対策を一通りカバーしたい方には、Wordfence Securityが最も安心できる選択です。
iThemes Security – 簡単なUIで初心者向け
iThemes Securityは、初心者にもやさしい設計が特長のプラグインです。
難しい設定がなく、画面の指示に従うだけで簡単にセキュリティ対策ができます。
不正ログインの防止やデータベースの保護など、基本機能が充実しています。
また、ダッシュボードでセキュリティ状況をひと目で確認できるため、管理がしやすいのも利点です。
WordPressを始めたばかりの人には、iThemes Securityがもっとも扱いやすいプラグインです。
Sucuri Security – 外部攻撃からの保護に強い
Sucuri Securityは、外部からの攻撃をブロックする機能に特化したプラグインです。
特にDDoS攻撃やマルウェアの検出に強く、クラウドベースの保護機能も利用できます。
ログの記録やファイルの改ざんチェックも可能で、専門的な監視ができる点が評価されています。
米国のセキュリティ企業が開発しているため、信頼性も高いです。
大規模な攻撃に備えたい場合や、海外からのアクセスが多いサイトに向いています。
All In One WP Security – 無料で多機能
All In One WP Securityは、無料でありながら多機能なセキュリティプラグインです。
ログイン保護・データベースセキュリティ・スパム防止など、基本機能がすべてそろっています。
初心者から中級者まで使いやすい構成で、視覚的なスコア表示もあるため、状況を把握しやすいです。
コストをかけずに幅広い対策を行いたい人にとって、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢です。
無料でサイトを総合的に守りたいなら、All In One WP Securityは最適です。
WP fail2ban – ログイン試行のブロックに強み
WP fail2banは、ログインの試行回数を記録し、不審なアクセスを遮断することに特化しています。
ブルートフォース攻撃に対して強力な防御が可能で、サーバー側のログにも記録を残せます。
高度なセキュリティを求める中級者以上のユーザーにおすすめです。
Linuxサーバーのログ監視ツール「fail2ban」との連携により、攻撃者のIPアドレスを自動で遮断できます。
ログイン攻撃を確実に防ぎたい方にとって、WP fail2banは非常に有効な手段です。
サイト運営者が見落としがちなセキュリティの盲点
WordPressサイトの運営では、目立つ攻撃への対策ばかりに目が向きがちです。しかし、見落とされやすいポイントが原因で深刻な被害につながるケースもあります。ここでは、特に注意すべき3つの盲点を解説します。
バックアップの未設定で復旧が困難に
サイトに何か問題が起きたとき、復旧のカギとなるのがバックアップです。
バックアップとは、サイトのデータを定期的に保存しておくことです。これをしていないと、ハッキングや不具合のあとに元の状態へ戻すことができません。
例えば、ある店舗サイトでは不正アクセスによりページ全体が削除されましたが、バックアップがなかったため復元できず、一から作り直すことになりました。
「BackWPup」や「UpdraftPlus」などのプラグインを使えば、バックアップは自動で取れます。
日ごろからバックアップを取っておくことが、万が一のトラブル時にサイトを救う唯一の手段です。
フォームのバリデーション不足が招く危険
バリデーションとは、入力されたデータに問題がないかを確認するしくみです。
お問い合わせフォームなどにバリデーションが設定されていないと、不正なデータが送られてきて、サイト内部に影響を及ぼすことがあります。
たとえば、メールアドレス欄にスクリプト(=プログラムの命令文)を入れられると、他のユーザーの情報が抜き取られたり、悪意のあるリンクが送信されたりする可能性があります。
「Contact Form 7」や「WPForms」では、入力のチェック機能がついており、安全性を高めることができます。
フォームのバリデーション設定は、外部からの攻撃を防ぐために必須の作業です。
テスト環境のまま公開してしまうリスク
本番用とは別に用意するテスト環境は、機能やデザインの動作確認に使われます。
しかし、設定やパスワードが甘いまま公開すると、ハッカーにとって格好の標的になります。
たとえば、ある開発会社では、テスト環境をネット上に公開したまま放置していたため、そこから管理画面に侵入され、本番サイトのデータがすべて書き換えられました。
不要なテスト環境は削除し、アクセス制限をかけるなどの対策が必要です。
開発用の環境も含めて、すべての公開情報に対して同じレベルのセキュリティ意識を持つことが重要です。
WordPressサイトがハッキングされたときの初動対応と復旧手順
WordPressサイトがハッキングされたとき、慌てず冷静に対処することが何より大切です。間違った対応は被害を広げてしまうおそれがあります。ここでは、実際にハッキングされた場合に行うべき初動対応と復旧までの手順を4つに分けて説明します。
管理画面に入れるか確認する
まず最初に確認すべきなのは、管理画面にログインできるかどうかです。
ログインできる場合、早急に以下の対応を行うことができます。
- ユーザー情報の確認(見知らぬユーザーの追加がないか)
- 不正な投稿や変更がないかのチェック
- パスワードの変更
一方、ログインできない場合は、パスワードが変更されている、または管理者権限が削除された可能性があります。
その場合、次の手順としてサーバー側からの操作が必要です。
ログインできるかどうかで、対応の方法と緊急性が大きく変わるため、まず確認することが重要です。
サーバー会社に連絡して一時閉鎖する
被害の拡大を防ぐには、サイトへのアクセスを一時的に止めることが効果的です。
特に、マルウェアが仕込まれている場合、訪問者にも被害が及ぶ可能性があります。
すぐにレンタルサーバー会社に連絡し、状況を説明して一時閉鎖を依頼しましょう。
多くのサーバー会社では、不正アクセスへの対応窓口が設けられており、迅速なサポートが受けられます。
サイトの停止中に、原因の調査や復旧作業を進めることができます。
サイトの安全性が確認できるまでは、公開状態に戻さないことが鉄則です。
バックアップから復元し、不正ファイルを削除
バックアップがある場合、最も確実な復旧方法は「正常な状態に戻すこと」です。
復元作業は以下の手順で行います。
- 安全な日時のバックアップを選ぶ
- WordPress本体・データベース・アップロードファイルをすべて置き換える
- FTPソフトなどで不審なファイルがないか確認する
バックアップがない場合は、専門業者に復旧を依頼するしかありません。
また、不正なファイル名には以下のような特徴があります。
- 意味不明な英数字の羅列
- 本来存在しないディレクトリへの配置
- .php拡張子で極端にファイルサイズが小さい
サイトの信頼性を保つためには、被害の跡を確実に消す必要があります。
今後の被害を防ぐための再設定ポイント
復旧後、再びハッキングされないための設定を見直す必要があります。
主な見直しポイントは以下の通りです。
- すべてのパスワードを新しくする
- 不要なユーザーを削除する
- セキュリティプラグインの導入(例:Wordfence、iThemes Securityなど)
- 管理画面URLを変更する
- プラグイン・テーマを最新版に保つ
さらに、定期的なバックアップの設定と、不正アクセスの通知を受け取る設定も行いましょう。
再発防止には、初期設定だけでなく日々の管理と監視の意識が欠かせません。
WordPressのセキュリティ対策に関するよくある質問(FAQ)
WordPressの運営において、セキュリティに関する不安や疑問を感じる人は少なくありません。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について、具体的な回答とともにわかりやすく解説します。
無料テーマでも安全ですか?
無料テーマであっても、安全なものと危険なものがあります。
WordPress公式ディレクトリに掲載されている無料テーマは、一定の基準をクリアしており、安全性が確認されています。
一方で、非公式のサイトからダウンロードできる無料テーマには注意が必要です。
中には、悪意のあるコードが埋め込まれているものや、更新が何年も行われていないテーマも存在します。
実際に、非公式テーマを使用したサイトが改ざんされ、勝手に広告が表示されるようになった事例があります。
無料テーマを選ぶ場合は、必ずWordPress公式ディレクトリから入手することが安全対策につながります。
セキュリティ対策はプラグインだけで十分?
セキュリティプラグインは非常に有効ですが、それだけでは完全な対策とはいえません。
プラグインは外部攻撃の検知やブロック、マルウェアのスキャンなどを自動で行ってくれます。
しかし、以下のような運用面での管理も重要です。
- 強力なパスワードの使用
- 管理画面URLの変更
- 不要なプラグインやユーザーの削除
- 定期的なバックアップ
たとえば、プラグインを導入していても、弱いパスワードのまま放置していたためにログインを突破されたケースもあります。
セキュリティプラグインはあくまで「補助」であり、日常の設定や管理と組み合わせることで本当の効果を発揮します。
パスワードの使い回しは本当に危険?
はい、パスワードの使い回しは非常に危険です。
1つのサービスで情報が漏れた場合、同じパスワードを使っている他のサイトにも不正ログインされるおそれがあります。
これを「パスワードリスト攻撃」と呼びます。
たとえば、通販サイトで流出したパスワードが、そのままWordPressサイトのログインに使われて突破されるという事例があります。
このような攻撃は自動化されており、狙われた側に気づかれないまま被害が進むこともあります。
パスワードはサイトごとに別々のものを設定し、使い回しを絶対に避けることが安全の第一歩です。
セキュリティ強化のためにチェックしたい外部リソースと情報源
WordPressサイトの安全性を保つためには、最新のセキュリティ情報を常に把握しておくことが欠かせません。プラグインやテーマの脆弱性(弱点)は日々発見されており、早期の対応が被害防止につながります。ここでは、信頼性のある情報源を3つ紹介します。
JPCERTやIPAの脆弱性情報
JPCERT/CC(ジェーピーサート)とIPA(情報処理推進機構)は、日本の情報セキュリティに関する専門機関です。
どちらも最新の脆弱性情報を定期的に発信しており、WordPress関連の脅威も随時掲載されています。
たとえば、プラグインの脆弱性や標的型攻撃の傾向などが分かりやすくまとめられており、専門用語が苦手な方でも理解しやすい構成になっています。
公式サイト上では、以下のような情報が公開されています。
- 脆弱性の概要と影響範囲
- 修正方法や対策手順
- 最新の注意喚起情報
国内で安心して参照できる情報源として、JPCERTとIPAは最も信頼できる存在です。
WordPress公式のセキュリティブログ
WordPress.orgが提供する公式セキュリティブログも、重要な情報源のひとつです。
WordPress本体のアップデート情報や、開発チームによる修正履歴がリアルタイムで発信されます。
特に大規模な脆弱性が発見された場合、公式ブログ上でいち早く通知されることが多く、速やかな対応に役立ちます。
以下のような内容が掲載されています。
- セキュリティアップデートの内容
- 過去の脆弱性修正履歴
- 開発者向けのベストプラクティス
WordPressユーザーであれば、公式セキュリティブログを定期的に確認する習慣をつけることが重要です。
海外のセキュリティニュースサイト
世界的に使われているWordPressに関する最新情報は、海外の専門メディアでも多く取り上げられています。
特に以下のようなサイトは、セキュリティ業界でも信頼性が高く、情報の鮮度も優れています。
- The Hacker News(https://thehackernews.com)
- Krebs on Security(https://krebsonsecurity.com)
- BleepingComputer(https://www.bleepingcomputer.com)
これらのサイトでは、新たなマルウェアの動向や、国際的なサイバー攻撃の情報もカバーしています。
英語での情報提供となりますが、Google翻訳などを使えば、内容の把握は十分可能です。
グローバルな視点からセキュリティを強化したい場合、海外のニュースサイトは有益な情報源となります。
まとめ|WordPressサイトの安全は日々の対策と意識がカギ
この記事では、WordPressがハッカーに狙われやすい理由と、具体的な攻撃手口、さらに対策方法について詳しく解説しました。
①世界的な利用率と脆弱性が原因で攻撃対象になりやすい
②ブルートフォースやマルウェアなど実際の手口を紹介
③管理画面URL変更や2段階認証など今すぐできる対策を解説
④おすすめのセキュリティプラグインを5つ紹介
⑤見落としがちな盲点やハッキング時の対応手順も掲載
WordPressサイトを守るには、基本的な設定や日常の運用、そして信頼できる情報源からの最新情報が欠かせません。まずは小さな一歩からでも実行し、被害を未然に防ぐ意識を持ちましょう。
ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webのことは全然わからないので、一からしっかり説明してくれるWeb制作会社を探している」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。