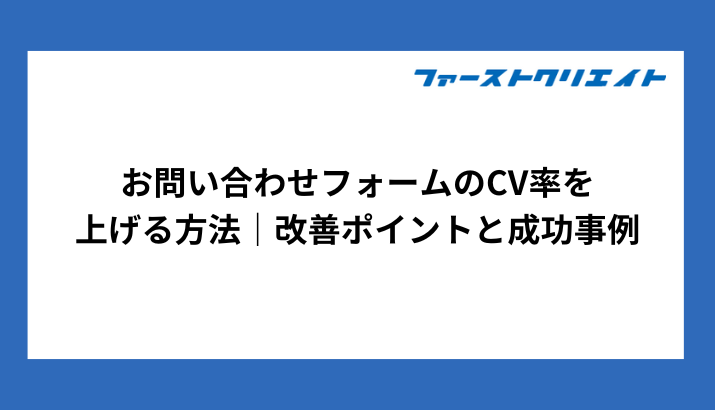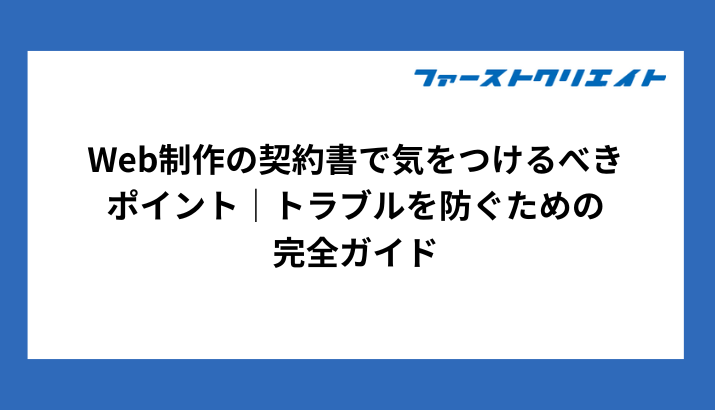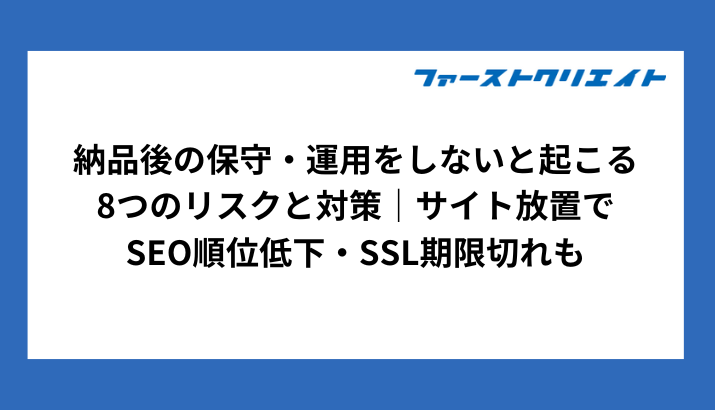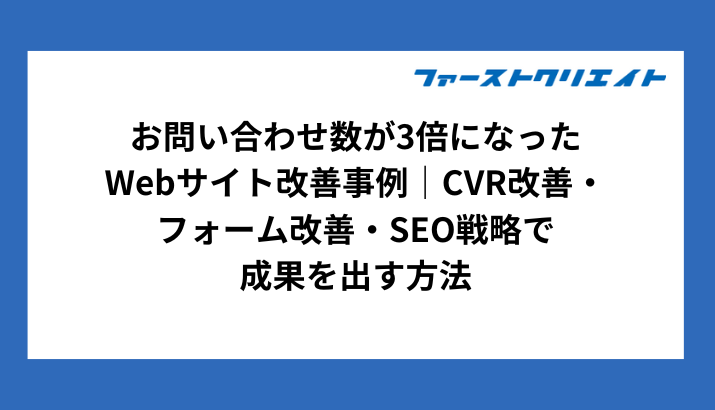定期的な更新がWebサイトを強くする理由とは?SEO効果・検索順位向上・信頼性を高める実践ポイント
2025年9月19日
お問い合わせ数が3倍になった Webサイト改善事例|CVR改善・ フォーム改善・SEO戦略で 成果を出す方法
2025年10月3日- お問い合わせフォームのCV率を上げたい
- 入力途中でユーザーが離脱してしまう
このようなお悩みはありませんか?
お問い合わせフォームは、入力設計やデザインを工夫することでCV率を高められます。スマホ対応やセキュリティ対策を行うだけでも成果が変わります。さらに、ABテストやCTAの改善を重ねることで、ユーザーに安心感を与えながら送信完了へ導けます。
そこで、この記事ではお問い合わせフォーム改善に悩む方へ向けて、CV率を上げる方法や具体的な成功事例を解説します。内容を読むことで、フォーム改善のポイントが理解でき、離脱を防ぎ成果につながる実践策が得られます。ぜひ最後までご覧ください。
お問い合わせフォームのCV率が低い主な原因
お問い合わせフォームのCV率が思うように上がらない場合、原因はユーザーの離脱にあります。入力作業や表示環境、安心感の不足などが重なると、送信完了まで進まず途中でやめてしまいます。以下では代表的な原因を解説します。
入力項目が多すぎてユーザーが離脱する
お問い合わせフォームで入力項目が多すぎると、ユーザーは途中で負担を感じて離脱します。必要な情報をすべて集めたいと考えても、入力欄が長いと「時間がかかりそう」と思われてしまいます。結果的に送信前にページを閉じられてしまいます。
例えば名古屋のWeb制作会社に依頼を検討しているユーザーが、名前やメールアドレスに加えて住所や年収まで求められた場合を想像してください。不要な項目があるだけで「なぜ必要なのか」と疑念を抱き、信頼感を失います。
効果的に情報を集めたいなら、必須項目は最低限に絞り込みましょう。以下のような工夫が有効です。
- 氏名とメールアドレスを中心にする
- 電話番号は必須にせず任意入力にする
- 具体的な相談内容は自由記入欄でまとめてもらう
入力欄を整理することで、ユーザーの心理的なハードルを下げられます。つまり、項目を減らすだけでCV率は確実に改善します。
スマホ対応が不十分で入力しづらい
スマートフォンからのアクセスが増える中、入力画面が最適化されていないと大きな離脱要因になります。文字が小さい、入力欄がずれている、ボタンが押しにくいといった状況では、ユーザーは操作を続ける意欲を失います。
例えば、指でタップしにくい小さな送信ボタンや、画面幅に収まらない入力欄は、ストレスを与える典型例です。名古屋のWeb制作会社の調査でも、モバイル対応が不十分なフォームは送信完了率が大幅に低下すると報告されています。
改善策としては次のような工夫が考えられます。
- レスポンシブデザインを導入して画面サイズに合わせる
- 入力欄やボタンを指で押しやすい大きさに設定する
- 自動入力機能を活用して入力時間を短縮する
フォームをスマートフォンに最適化することは、利便性を高めるだけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。モバイル対応を徹底することが、CV率改善には不可欠です。
セキュリティや信頼性に不安を与えている
ユーザーは個人情報を入力する際に、少しでも不安を感じると送信をためらいます。SSL非対応、運営会社の情報不足、プライバシーポリシーが不明確といった状況は「このサイトは安全なのか」と疑念を生みます。
例えば、お問い合わせフォームのURLが「http」から始まっている場合、ブラウザに警告が表示されることがあります。この時点で離脱するユーザーは少なくありません。さらに会社概要や運営者の連絡先が記載されていないと、匿名性が強調され不安が増します。
不安を解消するには、次のような取り組みが重要です。
- SSL(暗号化通信)を導入する
- 会社名や所在地を明記して安心感を与える
- プライバシーポリシーをわかりやすく掲載する
ユーザーに安全性を示すことで、安心して情報を入力してもらえます。信頼性を高める工夫が、フォーム送信のハードルを下げCV率を改善します。
お問い合わせフォームのCV率を上げる基本的な考え方
お問い合わせフォームのCV率を上げるには、入力欄を減らすだけでは足りません。ユーザーの心理を理解し、送信までの負担を軽くし、行動を促す工夫が必要です。以下では基本的な考え方を整理して解説します。
ユーザー心理を理解することの重要性
CV率改善の第一歩は、ユーザー心理を理解することです。フォームにたどり着いた人は「問い合わせたい」という意欲を持っていますが、同時に「入力が面倒」「個人情報が心配」といった不安も感じています。その心理を考慮せずに設計すると、離脱の原因になります。
例えば、名古屋のWeb制作会社に問い合わせをしようとした人が、必要以上に細かい情報を求められた場合を想像してください。安心して入力する気持ちよりも「ここで個人情報を出しても良いのか」という不安が勝ち、送信前に離脱してしまいます。
ユーザー心理を理解するための工夫は以下の通りです。
- 入力の負担を減らす設計を心がける
- 安心感を与える情報をフォーム周辺に記載する
- 送信後にメリットを得られると伝える
ユーザーの立場に立ち、不安を和らげる配慮がCV率改善の出発点です。
送信完了までのストレスを最小化する工夫
フォーム入力でストレスを感じると、ユーザーは途中でやめてしまいます。小さな不便が積み重なり、最終的に送信を断念することも珍しくありません。そこで重要なのが、ストレス要因を徹底的に減らすことです。
例えば、入力欄のエラーメッセージが「正しくありません」とだけ表示されると、どこを直せば良いのか分からず混乱します。改善するには「メールアドレスには@が必要です」といった具体的な案内が必要です。
ストレスを減らす工夫の例は次の通りです。
- 入力補助機能を導入して自動で候補を表示する
- 必須項目を明確に表示し、エラー箇所を赤字で示す
- 入力完了後の確認画面をシンプルに設計する
小さな不便を取り除くことで、ユーザーは安心して最後まで進み、結果的にCV率が向上します。
CTA(行動喚起)の見直しと改善
CTAとは「Call To Action」の略で、行動を促すための言葉やボタンのことです。フォームの送信ボタンにどんな言葉を使うかで、CV率は大きく変わります。「送信」という無機質な言葉よりも「無料で相談する」「資料を受け取る」のように具体的な行動を示すと効果的です。
例えば、名古屋のWeb制作会社が「送信」ではなく「無料相談を申し込む」と書き換えたところ、送信数が増加したケースもあります。ユーザーに「送信することで得られるメリット」を伝える表現に変えることで、行動への抵抗感を軽減できます。
CTAを改善するポイントは以下です。
- 行動後のメリットを具体的に伝える言葉を使う
- ボタンの色や大きさを視認性の高いデザインにする
- ページ内でボタンを複数配置して機会を増やす
CTAの見直しによってユーザーの背中を押せるため、フォーム改善の中でも効果が出やすい施策といえます。
デザインとUIでお問い合わせフォームを改善する方法
お問い合わせフォームは見やすさや使いやすさが大切です。デザインやUI(ユーザーインターフェース)が整っていないと、途中で離脱される原因になります。ここでは、CV率を上げるために効果的なデザイン改善の考え方を解説します。
スマホ・タブレット対応のレスポンシブデザイン
現在はスマートフォンやタブレットからのアクセスが主流です。画面幅に合わせて自動的に最適化されるレスポンシブデザインを導入することは必須です。小さな画面でも入力欄が見やすく、ボタンが押しやすいことで離脱を防げます。
例えば、名古屋のWeb制作会社に問い合わせるユーザーが電車内でスマートフォンから入力するとき、文字が小さくて見にくいフォームでは途中で諦めてしまいます。逆に幅に合わせて自動調整されるフォームなら、最後まで入力が続きやすくなります。
レスポンシブデザイン導入の工夫は以下の通りです。
- 入力欄やボタンを画面幅に合わせて自動調整する
- フォントサイズを読みやすい大きさに設定する
- 横スクロールが不要なシンプルなレイアウトにする
モバイル対応を整えることで、どの端末からでも快適に使えるフォームとなり、CV率向上につながります。
ボタンや配色を工夫してクリック率を高める
送信ボタンのデザインや色は、ユーザーの行動に直結します。目立たない色や小さなサイズでは、押すべき場所がわかりにくく離脱の要因になります。視認性が高く、クリックしたくなる工夫が必要です。
例えば「送信」ボタンが背景と同じ色合いだと気づかれにくくなります。反対に、背景色とコントラストをつけたオレンジや青などを使えば、自然と視線が集まりクリック率が高まります。さらにホバー時に色が変化すると、押したい気持ちが強まります。
改善のポイントは次の通りです。
- 背景色と異なる強調色を使ってボタンを目立たせる
- マウスオーバー時やタップ時に色や影を変化させる
- ページの下部だけでなく途中にもボタンを設置する
ボタンや配色を工夫するだけで、行動を促す効果が高まり、CV率改善に直結します。
入力中の離脱を防ぐためのUX改善策
UX(ユーザー体験)とは、ユーザーが操作する際の使いやすさや快適さを指します。入力途中でストレスを感じると離脱が増えるため、UXを意識した設計が重要です。小さな不便を取り除くことがCV率改善の近道になります。
例えば、入力エラーがどこにあるのか分かりにくいと、ユーザーは苛立ちを感じて途中でやめてしまいます。そこでリアルタイムでエラーチェックを行い、赤字で具体的に修正点を表示すると、スムーズに修正できます。
UXを改善する工夫は以下の通りです。
- 入力中に自動保存機能を導入して途中離脱を防ぐ
- リアルタイムでエラーを表示して修正を簡単にする
- 入力補助(住所自動入力など)を取り入れる
ユーザーが快適に入力を続けられる環境を作ることで、離脱を防ぎCV率を高められます。
信頼性を高めることでCV率を上げる方法
お問い合わせフォームは、ユーザーが個人情報を入力する場です。安心感が欠けると、途中で送信をやめてしまう原因になります。そこで信頼性を高める仕組みを整えることがCV率向上につながります。ここでは効果的な方法を紹介します。
SSL対応やセキュリティ表記を明示する
SSLとは、入力されたデータを暗号化して安全に送受信する仕組みのことです。フォームがSSL対応していないと「保護されていません」という警告が表示され、ユーザーは不安を抱きます。これだけで送信を断念される可能性が高まります。
例えば、名古屋のWeb制作会社の調査では、SSLを導入していないフォームは離脱率が高くなる傾向が見られます。SSL対応をしているサイトでは「https」で始まり、鍵のマークがブラウザに表示されるため、安心感を与えられます。
さらにフォーム周辺に「SSLで保護されています」などの表記を加えると、ユーザーは安全性を理解しやすくなります。セキュリティ対応を明示するだけで、信頼感が高まりCV率改善につながります。
会社情報・プライバシーポリシーを明確にする
ユーザーは「どの企業に情報を送るのか」を気にしています。会社名や所在地が不明確だと不安になり、送信をためらいます。そのため、会社情報やプライバシーポリシーを明確に提示することが重要です。
例えば、フォームの下部やサイドに「運営会社:〇〇株式会社(所在地:名古屋市)」と記載するだけで安心感が増します。プライバシーポリシーには「取得した個人情報は目的以外で使用しません」といった文言を入れると、信頼性が高まります。
補足として、以下の内容を明記すると効果的です。
- 会社名、所在地、電話番号
- 担当部署や責任者の氏名
- 個人情報の取り扱い方針(プライバシーポリシー)
ユーザーが送信に迷わないよう、透明性を示すことがCV率向上の鍵になります。
フォーム送信後のサンクスページで安心感を与える
フォームを送信した後に表示されるサンクスページは、信頼性を補強する大切な役割を持ちます。送信完了のメッセージがあることで「正しく送れた」という安心感を与えられます。逆に何も表示されないと、不安が残り再度の問い合わせをためらわせます。
例えば「お問い合わせありがとうございます。名古屋のWeb制作会社〇〇が確認次第ご連絡いたします」と表示するだけで、安心感は大きく変わります。さらに返信までの目安時間を明示すると、ユーザーの不安を減らせます。
効果的なサンクスページの要素は次の通りです。
- 送信が完了したことを伝えるメッセージ
- 返信までの目安時間や担当部署を記載
- 次の行動につながる案内(サービス紹介ページなどへのリンク)
サンクスページでのフォローが安心感を高め、結果としてCV率をさらに引き上げます。
ABテストでフォーム改善効果を検証する方法
お問い合わせフォームの改善は、一度で最適解にたどり着けるとは限りません。改善の有効性を確かめるには、ABテストを実施してデータに基づいて判断することが重要です。ABテストとは、2つ以上のパターンを用意し、どちらが効果的かを比較する方法です。ここでは具体的な検証の進め方を紹介します。
フォーム長さや入力項目の違いを比較する
入力項目の数やフォームの長さはCV率に直結します。そこでABテストを行い、短いフォームと長いフォームを比較することが効果的です。必須項目を減らしたシンプルなパターンと、詳細情報を求めるパターンを用意し、送信完了率を測定します。
例えば、名古屋のWeb制作会社が「氏名とメールアドレスのみ」のフォームと「氏名・メールアドレス・電話番号・住所」を求めるフォームを比較した場合、前者の方が完了率が高くなるケースが多いです。ユーザーは負担が少ない方を選ぶ傾向があるためです。
このテストで得られた結果は、今後のフォーム設計に大きなヒントを与えます。実際のデータに基づいて最適な項目数を決定することがCV率向上につながります。
CTAボタンの色や文言をテストする
CTAボタンはフォーム改善の中でも効果が出やすい要素です。ABテストでは、ボタンの色や文言を変えてクリック率を比較します。「送信」よりも「無料で相談する」や「資料を請求する」といった具体的な表現に変えるだけで成果が変わります。
例えば、青色ボタンとオレンジ色ボタンを比較した場合、背景とのコントラストが強い色の方が注目されやすくなります。さらに文言を「送信」から「無料相談を申し込む」に変えると、心理的な抵抗感が減り、クリック率が向上する事例があります。
このようにボタン1つの変更でも結果が大きく変わることがあるため、積極的にテストを行う価値があります。CTAの最適化は少ない労力で成果を高められる有効な施策です。
成果の分析と次の改善につなげる
ABテストは実施するだけでは意味がありません。結果を正しく分析し、次の改善に活かすことが大切です。クリック率や送信完了率だけでなく、フォーム到達から送信までの時間や途中離脱率も確認する必要があります。
例えば、名古屋のWeb制作会社が実施したテストで、入力項目を減らすと送信数は増えましたが、内容が不十分で商談につながらないケースが増えたという結果が出ました。この場合は、項目数を減らす代わりに自由記入欄を工夫するなど、次の改善策を検討できます。
分析で注目すべき指標は以下の通りです。
- 送信完了率(CV率)
- 離脱率(どの段階で離脱したか)
- 送信内容の質(商談や成約につながったか)
ABテストの成果を正しく分析し、継続的に改善を重ねることで、フォームの完成度が高まりCV率も安定して上昇します。
成功事例から学ぶお問い合わせフォーム改善ポイント
理論だけでなく、実際の事例から学ぶことは非常に有効です。お問い合わせフォームの改善は、業種や企業規模に関係なく効果を発揮します。ここではBtoB企業、ECサイトやサービス業、中小企業の事例を紹介し、具体的な改善のヒントを解説します。
BtoB企業におけるCV率改善事例
BtoB企業の場合、問い合わせ内容が商談につながる可能性が高いため、フォームの改善効果が大きく表れます。ある名古屋のWeb制作会社では、入力項目を精査して「会社名・氏名・メールアドレス・相談内容」の4つに絞った結果、CV率が30%向上しました。以前は部署名や電話番号を必須にしていたため、入力の負担が大きく離脱が目立っていたのです。
さらに、送信後のサンクスページで「1営業日以内に担当者がご連絡します」と明示したことで、ユーザーの安心感が増し、成約率の向上にもつながりました。BtoB企業では、必須項目を最小限に絞り、迅速な対応を保証することが効果的です。
ECサイトやサービス業でのフォーム最適化事例
ECサイトやサービス業では、商品購入や予約への導線としてフォームが使われます。ここでは「スムーズに入力できるか」が鍵となります。あるサービス業の事例では、スマートフォンに最適化したレスポンシブデザインを導入し、入力補助として住所の自動入力機能を取り入れました。その結果、スマートフォン経由の送信数が約1.5倍に増加しました。
また、CTAボタンの文言を「送信する」から「無料で予約する」に変更したところ、心理的なハードルが下がり、予約数の増加につながりました。ECやサービス業では、操作の簡単さと心理的負担の軽減がCV率改善に直結します。
中小企業でも実践できる低コスト改善方法
中小企業の場合、大規模なシステム改修は難しいですが、低コストでできる改善でも十分な効果が得られます。例えば、入力項目を減らすだけでも離脱率を下げられます。さらに、フォーム周辺に「SSL対応済み」「個人情報は第三者に提供しません」といった一文を追加するだけで、信頼感を高めることが可能です。
名古屋の中小企業の例では、既存のフォームに色のコントラストを強調した送信ボタンを導入し、さらに「24時間以内に返信します」と明記しただけでCV率が20%以上改善しました。大きな投資をせずとも、ユーザーに安心感を与える工夫を加えることで成果が出せます。
中小企業でも、入力項目の整理や簡単なUI改善など小さな工夫を積み重ねることで、確実にCV率を上げることができます。
よくある質問|お問い合わせフォーム改善の疑問解消
お問い合わせフォームの改善を進める中で、多くの企業が共通して抱く疑問があります。ここでは代表的な質問に答えることで、改善を具体的に進める際の参考にしていただけます。
フォームの最適な入力項目数は?
入力項目の数は少ないほどCV率が高まる傾向があります。ただし、情報が不足すると商談や対応がスムーズに進まない可能性もあるため、目的に応じて最適化することが重要です。基本的には「氏名」「メールアドレス」「問い合わせ内容」の3項目を中心に設計するのが効果的です。
例えば、名古屋のWeb制作会社では以前「住所・電話番号・部署名」を必須にしていましたが、項目を3つに絞った結果、送信率が約1.4倍に増加しました。最適な入力項目数は3〜5項目が目安であり、必須以外は任意にするのが理想です。
スマホ対応で特に気をつけるべき点は?
スマートフォンからのアクセスが増えている今、フォームがスマホに適していないと離脱の大きな要因になります。特に注意すべき点は「入力のしやすさ」と「ボタンの押しやすさ」です。文字が小さすぎたり、入力欄が画面からはみ出したりすると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
具体的な工夫としては以下が効果的です。
- 入力欄とボタンを指でタップしやすい大きさに設定する
- 自動入力機能を導入して入力時間を短縮する
- 横スクロール不要のシンプルなレイアウトにする
スマホ対応では「片手で操作できるか」を基準に設計することが重要です。
ABテストはどのくらいの期間行うべき?
ABテストの期間は、十分なデータが集まるまで続けることが基本です。短期間では偶然の要素に左右される可能性があるため、最低でも2週間以上は実施することが推奨されます。アクセス数や送信数が少ない場合は、1か月以上のデータを取る方が信頼性が高まります。
例えば、名古屋のWeb制作会社がCTAボタンの色をテストした際、1週間目では青が有利でしたが、3週間のデータを集めると最終的にオレンジの方が効果的であることが判明しました。ABテストは2〜4週間を目安に行い、十分なサンプル数を確保することが成果を正しく判断する鍵です。
まとめ|お問い合わせフォーム改善でCV率を着実に上げる
お問い合わせフォームのCV率を高めるには、複数の観点から改善を積み重ねることが重要です。入力項目の最小化やモバイル対応、セキュリティの強化はすぐに取り入れられる基本施策です。さらに、CTAボタンの工夫やABテストによる検証を繰り返すことで、データに基づいた改善が可能になります。
また、BtoB企業、ECサイト、サービス業、中小企業など、どの業種でも共通して言えるのは「ユーザー心理に寄り添い、ストレスなく入力できるフォームを整えること」が成功の鍵だという点です。名古屋のWeb制作会社でも、実際にフォームの最適化でCV率を大幅に改善した事例が存在します。
つまり、お問い合わせフォームの改善は小さな工夫の積み重ねが大きな成果につながります。信頼性と使いやすさを意識して改善を続けることで、CV率は着実に向上します。
ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webのことは全然わからないので、一からしっかり説明してくれるWeb制作会社を探している」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。