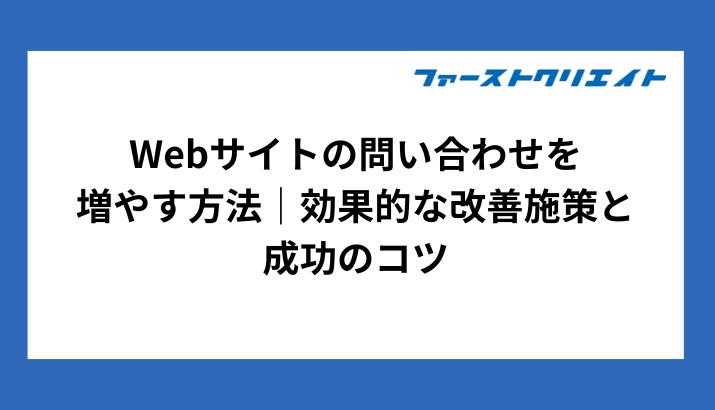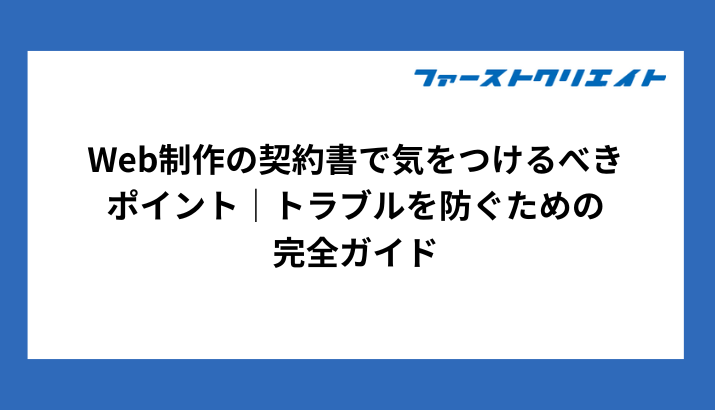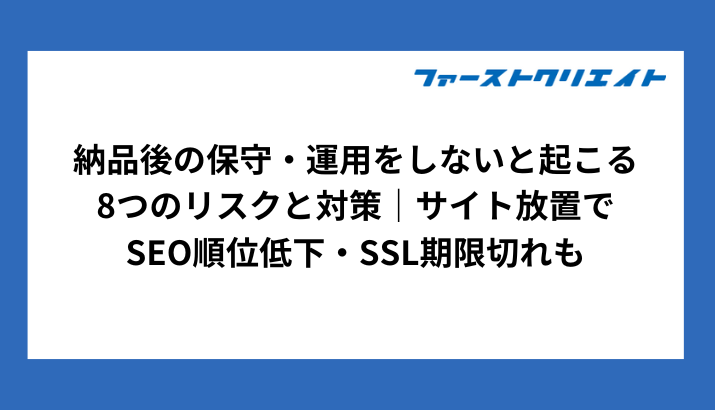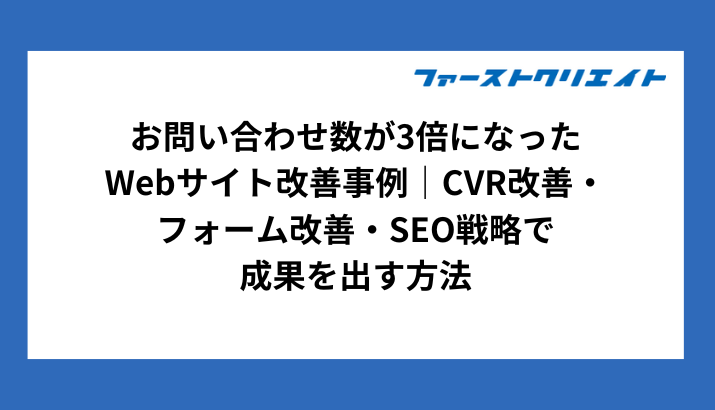MTMLとは?Movable Type初心者必見!使い方・構文・タグ一覧・活用事例をまるごと解説
2025年6月27日
ドメインの選び方完全ガイド|初心者でも失敗しないポイント
2025年9月3日- Webサイトからの問い合わせが思うように増えない
- フォームを設置しても利用者が途中で離脱してしまう
このようなお悩みはありませんか?
Webサイトの問い合わせ数を増やすには、集客施策や導線設計、信頼性の向上といった複数の要素を整えることが欠かせません。改善ポイントを押さえることで、利用者は迷わず行動でき、成果につながります。
そこで本記事では、問い合わせ件数を伸ばしたい方へ向けて、フォーム改善・SEO対策・事例紹介など具体的な方法を解説します。読み進めることで、自社サイトの課題が見え、効果的な改善策を実践できます。ぜひ最後までお読みください。
Webサイトの問い合わせを増やすには?基本的な考え方
Webサイトからの問い合わせを増やすためには、まず現状を正しく把握し、改善の方向性を明確にする必要があります。多くの場合、問い合わせ数が伸びない原因は単一ではなく、複数の要因が組み合わさっています。そのため、まずは課題を整理し、次に効果的な改善策を選択することが重要です。
問い合わせ数が伸びない原因とは
問い合わせが増えない場合、主に以下のような原因が考えられます。
- Webサイトへの訪問者が少ない
- 問い合わせフォームまでの導線がわかりにくい
- サービスや商品の説明が不十分で信頼を得られない
訪問者が少なければ、そもそも問い合わせ件数が増えることはありません。さらに、問い合わせフォームまでの導線が複雑であると、利用者は途中で離脱してしまいます。説明不足や実績の提示不足も信頼を損なう要因となります。つまり、集客不足・導線設計の不備・信頼性の欠如の3点が大きな課題となります。
問い合わせを増やすために重要な3つの要素(集客・導線・信頼)
問い合わせ件数を増やすためには、次の3つの要素をバランスよく改善することが必要です。
- 集客:検索エンジン対策(SEO)や広告を活用して訪問者を増やす
- 導線:問い合わせボタンやフォームをわかりやすい位置に配置する
- 信頼:事例紹介や利用者の声を掲載して安心感を与える
例えばSEOとは、検索エンジンの検索結果で自社のWebページを上位に表示させるための取り組みを指します。検索結果で上位表示されることで訪問者数が増え、問い合わせのチャンスも広がります。また導線設計では、問い合わせボタンをページの上部や記事の終わりに置くと利用者が迷わず行動できます。さらに、実績やお客様の声を掲載すると不安を解消しやすくなり、問い合わせ率は向上します。
つまり、集客・導線・信頼の3つを同時に高めることが、Webサイトの問い合わせを増やすための基本的な考え方です。
問い合わせを増やすためのWebサイト改善ポイント
Webサイトからの問い合わせを増やすには、見た目や使いやすさを意識した改善が欠かせません。利用者が迷わずフォームにたどり着き、安心して送信できる設計を整えることが重要です。ここでは、特に効果が大きい4つの改善ポイントを紹介します。
CVR(コンバージョン率)を高めるデザインとレイアウト
CVRとは、サイトを訪れた人のうち実際に問い合わせや購入に至った割合を示す数値です。この割合を高めるには、デザインとレイアウトの最適化が重要です。見やすい文字サイズや余白を確保すると、情報が伝わりやすくなります。さらに色使いを工夫すると、利用者は重要な部分に自然と目を向けます。
例えば、信頼感を与える青や安心感を強める緑を基調にしたデザインは効果的です。文字情報を詰め込みすぎず、視線の流れを意識したレイアウトにすると、利用者はスムーズに行動できます。デザインとレイアウトの改善は、問い合わせ数の増加に直結します。
CTA(問い合わせボタン)の配置と目立たせ方
CTAとは「Call To Action」の略で、行動を促す要素を指します。Webサイトでは問い合わせボタンが代表的です。このボタンを適切な位置に置くことで、問い合わせ件数が大きく変わります。ページの上部やスクロール後も見える場所に設置すると、利用者は迷わず行動できます。
また、ボタンの色や文言も工夫が必要です。「お問い合わせはこちら」といった具体的な言葉を使い、背景とコントラストの強い色を選ぶことで視認性が高まります。適切な配置とデザインのCTAは、利用者の行動を後押しする強力な要素です。
フォームを簡単にする|入力項目を最小限に絞るコツ
問い合わせフォームは、入力項目が多すぎると離脱率が高まります。必要以上に住所や電話番号を求めると、利用者は面倒に感じて送信をやめてしまいます。そこで、入力項目を最小限に絞ることが重要です。
例えば、氏名・メールアドレス・問い合わせ内容の3項目に限定すると、入力の負担は大きく減ります。そのうえで、必要に応じて追加情報を後から聞く仕組みにすれば効率的です。入力のしやすさを意識することで、フォーム完了率が高まり、問い合わせ件数も増加します。
スマホユーザーを意識したレスポンシブ対応
近年はスマートフォンからのアクセスが大半を占めています。そのため、スマホ画面でも快適に利用できるレスポンシブ対応が不可欠です。レスポンシブ対応とは、画面サイズに合わせて自動的に表示を最適化する仕組みのことです。
ボタンや文字が小さすぎると誤操作が増え、問い合わせにつながりにくくなります。逆に指で押しやすいサイズに設計し、縦スクロールだけで完結する構成にすると、ストレスなく利用できます。スマホユーザーを意識したレスポンシブ対応は、問い合わせ増加に直結する改善策です。
コンテンツで問い合わせを増やす方法
Webサイトからの問い合わせ件数を増やすためには、訪問者が安心して行動できるように情報を届けることが大切です。その際に重要なのがコンテンツです。文章や画像、事例やSEO対策などを通じて、利用者に伝わりやすい形で情報を提示することで、信頼を得て行動につなげられます。
サービス内容をわかりやすく伝える文章と画像
問い合わせを増やすためには、サービスや商品の内容を誰でも理解できる形で伝えることが欠かせません。専門用語を多用すると理解しづらくなるため、できるだけ平易な言葉で説明することが大切です。さらに、文章だけでは伝わりにくい部分を補うために画像や図解を活用すると、利用者の理解が深まります。
例えば、Web制作サービスを提供している場合、完成後のサイトイメージをスクリーンショットで示すと具体的な効果が伝わります。また、価格体系や流れを図で説明すれば、利用者は安心して問い合わせが可能です。わかりやすい文章と補足画像を組み合わせることで、問い合わせへの障壁を下げられます。
事例紹介やお客様の声で信頼感を高める
利用者が問い合わせをためらう理由のひとつは「本当に信頼できるのか」という不安です。この不安を取り除くために効果的なのが事例紹介やお客様の声です。実際の成果や利用者の感想を掲載することで、第三者の証言が加わり信頼性が高まります。
例えば、過去の成功事例を「〇〇社では導入から3か月で問い合わせが倍増した」といった具体的な数字とともに紹介すると説得力が増します。お客様の声については、顔写真や会社名を添えるとさらに信頼感が強まります。実績や利用者の声を活用することは、信頼性を高め問い合わせ数を増やすための有効な手段です。
SEO対策でターゲット層の流入を増やす
問い合わせを増やすには、見込み客がWebサイトに訪れる機会を増やす必要があります。そのために欠かせないのがSEO対策です。SEOとは、検索エンジンの結果でWebページを上位に表示させるための取り組みを指します。検索結果で目立つ位置に表示されると、ターゲット層の流入が増え、問い合わせの可能性も広がります。
具体的には、サービス名や地域名など利用者が実際に検索しそうなキーワードを記事やページタイトルに含めることが効果的です。また、関連する情報を網羅的に提供することで検索エンジンから評価されやすくなります。SEO対策によってターゲット層の流入を増やすことは、問い合わせ件数を伸ばすための基盤となります。
集客施策で問い合わせを増やす
問い合わせ件数を伸ばすためには、サイトの改善だけでなく集客の強化も必要です。見込み客がWebサイトに訪れる数が少なければ、どれほどフォームやデザインを整えても効果は限定的です。ここでは、問い合わせにつながる代表的な集客施策を紹介します。
SNSや広告を活用して見込み客を増やす
SNSや広告は、多くの人にサービスを知ってもらうための有効な手段です。SNSでは情報発信を通じて企業の存在を身近に感じてもらえます。広告は費用がかかりますが、短期間でアクセス数を増やせる特徴があります。
例えばInstagramで施工事例や導入実績を写真付きで紹介すると、視覚的に魅力が伝わりやすくなります。Google広告を利用すれば、特定の地域や興味を持つ層に限定して表示できるため、効率的に見込み客を集められます。SNSと広告を適切に使い分けることで、短期的・長期的の両面で問い合わせ数を増やす効果があります。
SEOとリスティング広告を組み合わせるメリット
SEOとリスティング広告は、検索エンジンを利用した集客手法です。SEOは時間をかけて上位表示を目指す施策で、長期的な流入増加が期待できます。一方でリスティング広告は、費用を支払うことで即座に検索結果に表示でき、短期的な集客が可能です。
例えば「名古屋 ホームページ制作」のような地域×サービスのキーワードを広告で出すと、見込み客にすぐにリーチできます。同時にSEOで同じキーワードを対策すれば、自然検索と広告の両方で露出が増え、利用者の信頼感も高まります。SEOとリスティング広告を組み合わせることは、安定した集客と即効性の両立に効果的です。
LP(ランディングページ)の活用で成約率を高める
LPとは、特定の目的で作られる専用ページのことです。1つのサービスや商品に特化した情報を掲載し、訪問者に行動を促します。LPを活用すると、通常のWebサイトよりも問い合わせ率が高まる傾向があります。
例えば、キャンペーンや期間限定サービスを紹介するLPを作成し、広告から直接誘導すると効果的です。内容をシンプルにまとめ、画像やグラフを使って魅力をわかりやすく伝えることで、利用者は迷わず行動できます。LPを集客施策と組み合わせて運用することで、成約率を大きく高められます。
問い合わせを増やすためのユーザー心理へのアプローチ
問い合わせを増やすには、デザインや集客施策だけでなく、ユーザー心理に基づいた工夫も欠かせません。人は安心や信頼を感じたときに行動しやすくなります。そのため、心理的な不安を取り除き、安心してフォームを利用できる環境を作ることが重要です。
信頼を得るための権威性や実績の提示
利用者が問い合わせをためらう理由のひとつは「本当に信頼できるのか」という不安です。この不安を解消するためには、権威性や実績を明示することが有効です。権威性とは、専門的な知識や資格、受賞歴などによって信頼を裏付ける力を指します。
例えば、業界団体の認定を受けていることや、導入企業数・利用者数といった具体的な数字を示すことで、安心感が生まれます。さらに、メディア掲載実績を紹介すると第三者からの評価が加わり、信頼性は一層高まります。権威性と実績の提示は、ユーザーの不安を解消し、問い合わせへの行動を後押しする効果があります。
不安を解消するFAQやサポート情報の設置
問い合わせ前に不安を抱く利用者は少なくありません。その不安を解消するためには、FAQ(よくある質問)の設置が効果的です。FAQとは、利用者がよく疑問に思う内容とその回答をまとめたものです。事前に情報を提供することで、利用者は安心して行動できます。
例えば、「問い合わせ後の返信はどのくらいで来るのか」「費用は発生するのか」といった疑問を明記すると、利用者の不安は軽減されます。さらに、電話やメール以外にチャットやLINEでのサポート方法を提示すると利便性も向上します。FAQやサポート情報は、利用者の不安を事前に取り除き、問い合わせ率を上げる大切な仕組みです。
即時性を重視したチャットボットやLINE対応
現代の利用者はスピード感を求めています。そのため、即時に対応できる仕組みを導入することが効果的です。代表的な手段がチャットボットやLINE公式アカウントです。チャットボットは自動で回答するシステムで、24時間いつでも対応できる点が強みです。
例えば、問い合わせフォームを入力する前にチャットボットで質問に答えてもらえると、利用者の不安は大幅に解消されます。LINE対応を導入すると、利用者が普段から使い慣れているアプリでやり取りできるため、心理的なハードルが下がります。即時性のある対応手段は、利用者をスムーズに行動へ導き、問い合わせ増加に直結します。
Webサイトの問い合わせを増やす施策の成功事例
実際に問い合わせ数を増やすための施策を取り入れた事例を確認すると、自社に合った改善策を見つけやすくなります。ここでは、中小企業やサービス業で成果を上げた具体的な取り組みを紹介します。
中小企業の問い合わせ数が倍増した改善事例
ある中小企業では、問い合わせフォームまでの導線が複雑で、利用者が途中で離脱していました。改善として、トップページに問い合わせボタンを配置し、どのページからでもワンクリックでフォームに移動できるようにしました。その結果、導線が明確になり問い合わせ数は2倍に増加しました。
この事例から学べるのは、複雑な設計を見直し、利用者が迷わないシンプルな導線を整える重要性です。導線改善は小さな工夫であっても、大きな成果につながります。
フォーム改善でCVRが向上した事例
あるサービス業のサイトでは、問い合わせフォームに10項目以上の入力欄があり、利用者の負担が大きく離脱率が高い状態でした。そこで、必須項目を3つに絞り、残りは任意入力に変更しました。さらに入力補助機能を導入し、簡単に情報を記入できるようにしました。その結果、フォーム完了率が大きく上がり、問い合わせ件数も増加しました。
この事例からわかるのは、フォーム入力のしやすさが利用者の行動に直結するという点です。入力項目を見直し、負担を減らすことで問い合わせ率を確実に高められます。
コンテンツマーケティングによる問い合わせ増加の実例
ある不動産会社では、SEO対策を兼ねたコンテンツマーケティングを実施しました。具体的には、「引っ越し 費用の相場」や「住宅ローンの基礎知識」といった、利用者が知りたい情報を記事にまとめて発信しました。記事をきっかけにサイトを訪れた人が、そのまま問い合わせにつながるケースが増加しました。
この取り組みでは、ただアクセスを集めるだけでなく、見込み客が抱える疑問に答えることで信頼感を獲得できました。役立つコンテンツを提供することは、信頼を築き、問い合わせを自然に増やす効果的な方法です。
問い合わせ数を増やすための分析と改善サイクル
問い合わせ件数を増やすためには、一度施策を実施して終わりにするのではなく、データを分析して改善を繰り返すことが大切です。効果を測定し、課題を見つけて修正することで、継続的に成果を伸ばせます。ここでは具体的な分析方法と改善手順を紹介します。
GoogleアナリティクスでCVの流れを分析する方法
Googleアナリティクスとは、Webサイトの利用状況を解析できる無料ツールです。このツールを使うと、訪問者がどのページを見て問い合わせに至ったのか、またどのページで離脱したのかを確認できます。
例えば、サービス紹介ページから問い合わせフォームに移動する利用者が多い場合、そのページの改善が問い合わせ数に直結することがわかります。逆に、特定のページで離脱率が高ければ、内容や導線に問題があると判断できます。データに基づいて流れを分析することで、効率よく改善ポイントを特定できます。
A/Bテストで効果を検証するステップ
A/Bテストとは、2種類のページを用意して成果を比較する検証方法です。例えば、問い合わせボタンの色を「青」と「赤」に分けてどちらがクリックされやすいかを調べる、といった形で行います。
小さな変更でも結果に差が出ることがあり、最適なデザインや配置を見つけるうえで効果的です。テスト結果を記録して、改善の方向性を数値で確認すると信頼性の高い判断が可能です。A/Bテストは、感覚ではなく実データに基づいた改善を行うために欠かせない手法です。
定期的な改善で成果を持続させるポイント
問い合わせ数の改善は一度の調整で完結しません。検索エンジンのアルゴリズムやユーザーの行動は変化するため、定期的な見直しが必要です。改善サイクルを継続することで、成果を安定させることができます。
例えば、半年ごとにフォームの入力率を確認し、必要に応じて入力項目を見直すことが効果的です。また、新しい集客チャネルが登場した場合は積極的に取り入れると競合との差別化につながります。定期的な分析と改善を繰り返すことが、問い合わせ数を持続的に増やす秘訣です。
Webサイトの問い合わせを増やす際の注意点とよくある失敗
問い合わせ数を増やすための施策を実施しても、やり方を誤ると逆効果になることがあります。多くの企業が陥りやすい失敗を理解しておくことで、無駄な労力や機会損失を防げます。ここでは特に注意すべき失敗例を紹介します。
フォームを複雑にしすぎるリスク
入力項目を増やしすぎると、利用者は面倒に感じて離脱してしまいます。必要のない住所や電話番号を必須にすると、送信率は大きく下がります。フォームはシンプルに設計し、最小限の情報だけを求めることが重要です。
例えば「名前」「メールアドレス」「問い合わせ内容」の3つに絞ると、送信のハードルが下がります。追加情報が必要な場合は、返信時に改めて確認する仕組みにすると効率的です。フォームを複雑にしないことは、問い合わせ数を維持・増加させる基本的な注意点です。
集客ばかりで導線改善を怠る失敗例
広告やSEOでアクセス数を増やしても、問い合わせフォームまでの導線がわかりにくいと成果にはつながりません。アクセス数だけに注目して導線設計を軽視すると、投資が無駄になります。
例えば、ページの最下部にしか問い合わせボタンがない場合、利用者が途中で離脱してしまいます。ページの冒頭や記事の中にも設置することで、利用者はタイミングを逃さず行動できます。集客と導線改善を同時に進めることが、失敗を防ぐためのポイントです。
問い合わせ後の対応スピードの遅さによる機会損失
問い合わせを獲得できても、返信が遅いと利用者の関心は下がります。競合他社に先に対応される可能性もあり、大きな機会損失につながります。迅速な対応体制を整えることが、問い合わせを成果につなげるために欠かせません。
例えば、自動返信メールを送るだけでも「受け付けてもらえた」という安心感を与えられます。さらに、24時間以内に担当者から返信するルールを決めると信頼性が高まります。問い合わせ後の対応スピードを意識することは、成約率を上げるために必須の取り組みです。
まとめ|Webサイトの問い合わせを増やすには継続的な改善が必要
Webサイトの問い合わせ数を増やすためには、一度の施策で満足するのではなく、継続的な改善を行う姿勢が欠かせません。問い合わせ数を伸ばすための施策は、集客・導線・信頼といった複数の要素が組み合わさって成果を生み出します。そのため、どれか一つだけに偏るのではなく、全体をバランスよく見直すことが大切です。
今回紹介した施策を整理すると、以下のようになります。
- デザインやレイアウトを工夫してCVR(コンバージョン率)を高める
- 問い合わせフォームを簡単にして利用者の負担を減らす
- 事例紹介やお客様の声で信頼性を高める
- SEOや広告などの集客施策を活用する
- 分析やA/Bテストを通じて改善を繰り返す
これらの取り組みを継続することで、利用者が安心して行動できる環境が整い、問い合わせ数は安定して増えていきます。つまり、Webサイトの問い合わせを増やすには、一度の施策で終わらせず継続的に分析・改善を積み重ねることが成功の鍵です。